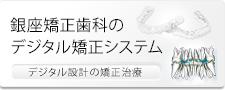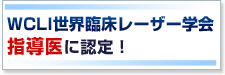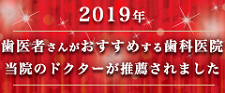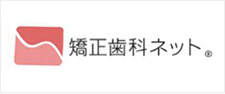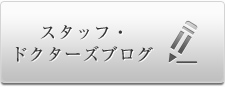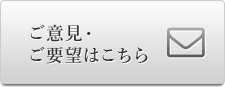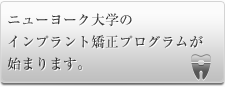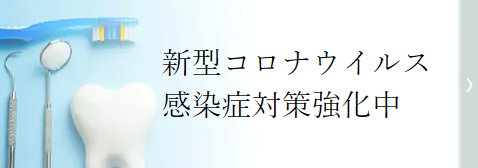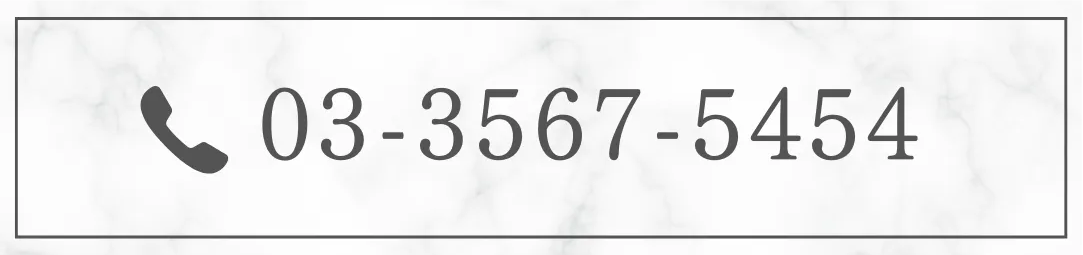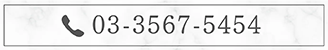こんにちは。銀座矯正歯科です。
顎の痛みや違和感、口の開けにくさといった症状が現れる顎関節症(がくかんせつしょう)は、日常生活に支障をきたすこともある身近なトラブルのひとつです。そしてその原因のひとつに「歯並びや噛み合わせの乱れ」が関係していることも。
矯正治療は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせを整えることで顎関節への負担を軽減できる可能性がある治療です。ただし、症状のある方は事前の診断や治療計画がとても重要で、場合によっては注意が必要なこともあります。
今回は、矯正治療と顎関節症の関係、治療によるリスクや改善の可能性、適切な対処法についてご紹介していきます。顎のトラブルに悩む方も、矯正を検討中の方も、ぜひご一読ください。
1.こんなお悩み、ありませんか?
 矯正治療を考えている患者様の中には、顎関節に違和感があることで不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
矯正治療を考えている患者様の中には、顎関節に違和感があることで不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
たとえば、
- 「口を開けたときにカクカク音が鳴るけれど、大丈夫?」
- 「矯正治療を始めたら、顎関節症がひどくなるって聞いて不安…」
- 「そもそも顎関節症があると矯正治療は受けられないの?」
こんな疑問やお悩みをよく耳にします。
私たち矯正歯科医の立場からお伝えすると、顎関節症があっても矯正治療がまったくできないわけではありません。ただし、治療前に顎の状態をしっかりと見極めて、必要な配慮をしながら治療を進めることが大切です。
矯正治療と顎関節症には密接な関係があり、正しい知識と判断で進めれば、顎の不調が改善されるケースもあります。反対に、顎の状態を無視して無理に進めてしまうと、かえって症状が悪化することもあります。
「矯正したいけれど、顎のカクカクが気になる…」という患者様も、どうぞご安心ください。まずは正しく知ることから始めてみましょう。
2.顎関節症とは?その症状と原因
 「口を開けたときにカクッと音がする」「あごが痛くて食事がつらい」「口が大きく開かない」
「口を開けたときにカクッと音がする」「あごが痛くて食事がつらい」「口が大きく開かない」
そんなお悩み、ありませんか?
それ、もしかすると顎関節症(がくかんせつしょう)かもしれません。
顎関節症は、あごの関節やまわりの筋肉に不調が出る状態のことで、年齢や性別を問わず多くの患者様が悩まれています。矯正治療とも関係が深いので、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
顎関節症の代表的な症状
顎関節症にはいくつかの代表的な症状があります。気になる症状がある場合は、早めの対処がおすすめです。
- ✅ あごを動かすと「カクカク」「ジャリジャリ」と音がする
- ✅ 口を開けたり噛んだりすると、あごの関節が痛む
- ✅ 口が大きく開かない、まっすぐ開けられない
- ✅ こめかみや首・肩まわりのコリや頭痛がある
軽い違和感程度で済む方もいれば、あごが動かなくなる「開口障害」まで進んでしまうケースもあります。
噛み合わせの乱れが関節に与える影響
実は、噛み合わせのズレや歯並びの乱れが、顎関節に大きな負担をかけていることがあります。例えば、奥歯できちんと噛めていない状態が続くと、あごの動きが不自然になり、関節や筋肉に負荷がかかってしまうんです。
また、上下の歯の位置関係がズレていると、左右の関節で力のかかり方がアンバランスになり、それが痛みや音の原因になることもあります。
特に矯正治療を検討されている患者様にとって、噛み合わせの見直しは顎関節へのケアの第一歩とも言えます。
生活習慣やストレスも影響します
顎関節症は、歯並びや噛み合わせだけでなく、日常のクセやストレスとも深く関係しています。
よくある生活習慣の例
- 📌 頬づえをつく
- 📌 スマホやパソコン作業中に前かがみの姿勢が多い
- 📌 食いしばりや歯ぎしりのクセがある
- 📌 片方だけで噛むクセがある
これらの習慣は、知らないうちにあごのバランスを崩してしまう原因になります。
また、ストレスがたまると無意識に噛みしめる癖が出やすくなり、筋肉が緊張して関節に負担をかけてしまうことも。
特に現代はストレス社会ですので、顎関節症の患者様が増えている背景には、こうした環境的な要因もあると言われています。
顎関節症は「放っておけば治る」というものではありません。初期のうちに気づき、正しい診断と対策をとることがとても大切です。
3.矯正治療で顎関節症は改善する?悪化する?
 「矯正をすると、あごの不調が治るって聞いたけど本当?」「逆に悪化することがあるって聞いて不安…」
「矯正をすると、あごの不調が治るって聞いたけど本当?」「逆に悪化することがあるって聞いて不安…」
こうしたご相談、実はとても多くいただきます。
結論からお伝えすると――矯正治療が顎関節症の改善につながることもありますが、治療の進め方によっては一時的に症状が強く出ることもある、というのが正直なところです。
矯正で顎関節症が改善するケースとは?
矯正治療がきっかけで、顎関節症の症状が軽くなるケースは実際に多くあります。
特に、以下のような場合です。
- 🦷 噛み合わせのズレが原因であごに負担がかかっていた
- 🦷 上下の歯がしっかり噛み合わず、あごの筋肉が疲れていた
- 🦷 あごをずらして噛むクセがあった(偏咀嚼)
こういった状況を矯正で整えることで、本来のバランスで噛めるようになり、関節や筋肉の負担が減るため、痛みや音などの症状が改善に向かうことがあります。
矯正中に一時的に症状が出ることもある理由
一方で、矯正治療を始めてしばらくすると、
- 「あごが少し重くなった」
- 「前よりカクッという音が気になる」
- 「顎関節のあたりが違和感ある」
といった一時的な症状が出ることもあります。
これは、歯が動くことで一時的に噛み合わせが不安定になる時期があるためです。
また、筋肉や関節が新しい動きに慣れるまでに少し時間がかかるため、慣れるまでの間に一時的な違和感や痛みが出ることがあります。しかしほとんどの場合は、治療が進むにつれて噛み合わせが整っていき、症状も落ち着いていきます。
必要に応じて、痛み止めや顎関節の負担を和らげる工夫もご提案できます。
矯正治療は「適切な計画」がカギです
大切なのは、患者様のお口の状態をしっかり見極めた上で、無理のない治療計画を立てることです。
顎関節症のリスクがある場合や、すでに症状が出ている場合は、以下のような点をしっかり考慮しながら進めます。
- ✔ 現在の噛み合わせ・あごの動きを詳細にチェック
- ✔ 顎関節の負担を最小限に抑える装置の選択
- ✔ 治療中も症状を定期的に確認し、必要に応じて計画を調整
また、顎関節症の症状が強い患者様の場合は、まず関節や筋肉の安定を優先してから矯正に進むというケースもあります。
矯正治療と顎関節症は、正しく理解しながら進めることで、お口全体の健康を大きく改善できる可能性を持っています。
「矯正で顎関節が悪化するのが怖い…」と心配な患者様こそ、専門的な知識と経験のある歯科医師にご相談いただければと思います。
4.顎関節症のリスクが高い歯並びとは?
 「自分の歯並びって、あごに負担をかけてるのかな?」
「自分の歯並びって、あごに負担をかけてるのかな?」
そんな疑問をお持ちの患者様もいらっしゃるかと思います。
実は、ある特徴のある歯並びの方は、顎関節症を起こしやすい傾向があるんです。
出っ歯・受け口など“あごのバランスが崩れている”歯並び
- 出っ歯(上顎前突):上の歯が前に出ていることで、前歯でうまく噛めず、あごを突き出すような動きになりがちです。
- 受け口(反対咬合・下顎前突):下の歯が前に出ている状態で、上下のあごのバランスが崩れ、あごの関節や筋肉に負担がかかりやすくなります。
こういった噛み合わせの乱れがあると、普段の会話や食事のたびに無意識に顎関節へストレスがかかるため、症状が出やすくなるんですね。
奥歯の噛み合わせが悪いと、関節にどう影響する?
奥歯がしっかり噛めていない状態、たとえば…
- 片方の奥歯だけが当たっている
- 噛むと前歯ばかりが当たる(奥歯が浮いている)
このような噛み合わせは、本来均等に負担を分け合うはずのあごの動きに偏りが生まれてしまい、特定の関節や筋肉に過度なストレスがかかってしまいます。
長く続くと、あごのだるさ・カクカク音・痛みなど、典型的な顎関節症の症状につながることも少なくありません。
片側ばかりで噛む癖があると要注意!
「いつも無意識に右ばかりで噛んでしまう」
「左側の奥歯が使いにくくて、自然と反対側で噛んでいる」
こういった“片噛み”の癖も、顎関節症の大きなリスクのひとつです。
✅片方にばかり負担がかかると…
- 関節のズレ
- 筋肉の緊張のアンバランス
- あごの動きのゆがみ
などが起きやすくなり、時間とともに関節の痛みや違和感として現れてくることがあります。
さらに、片噛みは歯並びの崩れを加速させてしまうため、噛み合わせと顎関節の悪循環を生むきっかけにもなりやすいです。
顎関節症は、初期の段階で気づいて対策をすれば悪化を防げることが多いです。
5.矯正治療を受ける際の重要なポイント
 顎関節症の症状がある患者様や、あごに違和感があるという方にとって、矯正治療を始める前に知っておいてほしいことがいくつかあります。
顎関節症の症状がある患者様や、あごに違和感があるという方にとって、矯正治療を始める前に知っておいてほしいことがいくつかあります。
矯正前の検査で「顎関節の状態」をしっかりチェック
矯正治療の前には、お口全体の状態を細かくチェックする精密検査を行います。
このとき、顎関節の動き方や左右のバランス、筋肉の緊張の度合いなども確認するのがとても大切です。
✅たとえば…
- 「口を開けるとカクッと音が鳴る」
- 「あごに違和感があるけど、痛みはない」
- 「朝起きたときにあごが疲れている感じがする」
こうした症状がある場合は、矯正治療を始める前に顎関節症の診断やケアを行う必要があります。
症状が軽くても、見逃さずに治療方針に組み込むことで、矯正中のトラブルを減らすことができます。
自分に合った矯正方法を選ぶことが大切です
患者様の顎関節の状態や噛み合わせのバランスによっては、矯正の方法を工夫することであごへの負担を軽くできることもあります。
✅たとえば…
- マウスピース矯正(インビザライン)は、あごの動きに合わせやすく、負担が比較的少ない場合があります。
- ワイヤー矯正は、しっかりとしたコントロールができるため、顎関節の調整を目的とする場合に有効なこともあります。
患者様のご希望やライフスタイル、症状の程度に合わせて、専門的な立場から一緒に治療法を選んでいくことが大切です。
治療中も油断せず「顎関節の状態」をこまめにチェック
矯正治療中は、歯が少しずつ動いていくため、あごへのバランスも日々変わっていきます。
✅このため、以下のような点に気をつけていただくと安心です:
- 定期的な検診であごの動きや噛み合わせを確認する
- 痛みや違和感が出たら、すぐに担当医に相談する
- ストレスや食いしばりなど、生活習慣の見直しも大切
また、あごをリラックスさせるための軽いマッサージや開口訓練などをご案内することもあります。治療中も一緒にサポートしていきますので、無理せず気になることはその都度ご相談くださいね。
顎関節症をお持ちの患者様にとって、「矯正治療で悪化したらどうしよう…」という不安はよくあるものです。
ですが、きちんと診断して、患者様に合った無理のない治療計画を立てれば、むしろ噛み合わせが整って症状が良くなることも少なくありません。
6.矯正中に顎関節症の症状が出た場合の対応策
 「矯正を始めてから、なんだかあごが痛くなった気がする」「口を開けるとカクッと音がするようになった」
「矯正を始めてから、なんだかあごが痛くなった気がする」「口を開けるとカクッと音がするようになった」
そんなふうに、矯正治療中に顎関節症のような症状が出てくることもあります。でも、慌てなくても大丈夫。
症状が出たときは、まず落ち着いて相談を
矯正中に顎関節に違和感が出ても、すぐに治療を中止しなければいけないというわけではありません。
まずは担当医にしっかり相談することが大切です。
こんな症状があれば、早めにお知らせください:
- 口を開けたときに「カクカク」「ジャリジャリ」と音が鳴る
- あごの周辺に痛みがある
- 口の開閉がしづらい・開けづらい
- 食事や会話であごが疲れやすい
放っておくと症状が悪化することもあるので、少しでも気になることがあれば遠慮なくお声がけください。
矯正装置の調整で症状がやわらぐこともあります
あごの関節や筋肉に負担がかかっている場合、装置の力が強すぎたり、歯の動き方に無理があることが原因になっているケースもあります。
その場合は、矯正装置の調整で症状が改善することがよくあります。
✅たとえば…
- ワイヤーの強さをやわらかく調整する
- マウスピースの段階を見直して、やさしい力で進める
- 一時的に歯の移動をお休みする
など、患者様の状態に合わせて無理のない治療に切り替えることができます。
矯正中だからといって、無理に進める必要はありません。治療はあごの状態と相談しながら、柔軟に進めていきましょう。
必要に応じて「スプリント療法」も併用します
症状が強い場合や、慢性的なあごの不調がある場合は、「スプリント療法」という治療を取り入れることがあります。
✅スプリント療法とは:
- 就寝時などに「スプリント」と呼ばれるマウスピースのような装置を装着
- あごの筋肉や関節の緊張をやわらげる目的で使用
- 食いしばりや歯ぎしりが強い方にも有効
矯正治療と並行して行うことで、症状の悪化を防ぎ、痛みや不快感を軽減できることがあります。
もちろん、スプリントの使用が必要かどうかは、症状の程度や原因をしっかり診断してから決めますので、心配せずにご相談ください。
矯正治療中に顎関節症の症状が出てしまったら、不安になるのは当然のことです。
「ちょっとおかしいな」と思ったときは、遠慮なくお話しくださいね。
7.顎関節症の予防とセルフケアの方法
 「口を開けるとカクカク音がする」「なんとなくあごがだるい」「朝起きるとあごが疲れている気がする」――
「口を開けるとカクカク音がする」「なんとなくあごがだるい」「朝起きるとあごが疲れている気がする」――
そんな症状が気になっている患者様へ。
顎関節症は、日常のちょっとした習慣やクセが原因になっていることも多いんです。
顎関節に負担をかけない“正しい噛み方”とは?
私たちは毎日、無意識のうちに“あご”を使っています。
噛み方に少し注意を向けるだけで、顎関節への負担を減らすことができます。
✅こんなポイントを意識してみましょう
- 片側ばかりで噛まない
→ どちらか一方ばかりで噛むと、左右の筋肉バランスが崩れて顎関節に負担がかかります。 - やわらかすぎるものばかり食べない
→ 適度に噛む力を使うことは、あごの筋肉を鍛える意味でも大切です。 - 食事中の姿勢にも注意
→ 猫背や顔を斜めに傾けた姿勢は、あごの動きに偏りが出やすくなります。
ちょっとした心がけが、顎関節を守る大きな一歩になりますよ。
あごのストレッチとマッサージでリラックス
忙しい毎日の中でも、ほんの数分でできるストレッチやマッサージはおすすめです。
あご周りの筋肉をほぐすことで、関節の動きがスムーズになり、痛みや違和感の予防にもつながります。
✅自宅でできる簡単ケア
- あごのストレッチ
口を無理なく「ゆっくり大きく開ける・閉じる」を10回繰り返す。
※痛みがある場合は中止してください。 - 側頭筋(こめかみ)のマッサージ
両手の指でこめかみをやさしくクルクルと円を描くようにほぐします。 - 首・肩まわりのストレッチ
あごの緊張は首や肩のコリともつながっています。デスクワークの合間にゆっくり回すだけでも◎。
「ちょっと疲れたな」と思ったときに、気軽に取り入れてみてください。
姿勢や生活習慣の見直しも大切です
顎関節症の原因は、あごだけにあるとは限りません。
姿勢や日常生活のちょっとしたクセが、知らないうちに顎関節に負担をかけていることも多いんです。
✅見直しておきたいポイント
- スマホを見るとき、首が前に出ていませんか?
→ スマホ首は、あごの関節にも負担がかかります。 - ほおづえをつくクセ、ありませんか?
→ あごの左右バランスが崩れやすくなります。 - 寝るときは横向きより仰向けがおすすめ
→ 横向き寝が習慣になっていると、あごの片側に圧がかかることも。 - ストレスや緊張がたまっていませんか?
→ 無意識の食いしばりや歯ぎしりの原因になります。
日々の生活の中で、あごにやさしい環境を作ることが大切です。
顎関節症は、日常のクセやストレスがきっかけで起こることが多い症状です。
でも、ご自身でできるちょっとしたケアを続けることで、予防や改善が十分に可能です。
あごの不調を感じたら、「疲れているサインかな?」と、ぜひ体の声に耳を傾けてあげてください。
8.矯正治療後の顎関節の安定性について
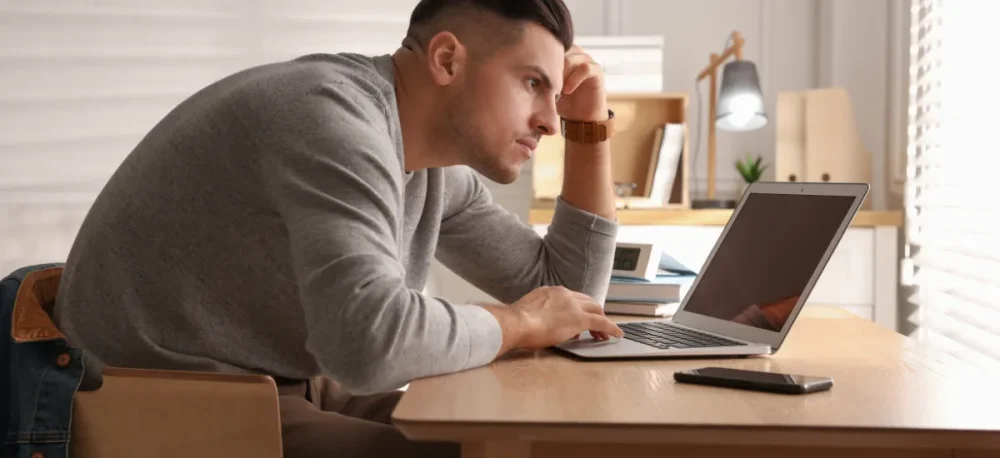 「矯正治療が終わったのに、またあごがカクカクしてきた…」
「矯正治療が終わったのに、またあごがカクカクしてきた…」
「せっかく歯並びを整えたのに、顎関節の不調がぶり返さないか不安」
そんなご不安をお持ちの患者様もいらっしゃるかと思います。
実は、矯正治療後のあごの状態を安定させるには、“その後のケア”がとても大切なんです。
矯正後に顎関節症が再発する可能性はあるの?
結論から言うと、「ゼロではありません」。
でも、きちんと保定やメンテナンスを行っていけば、多くの場合は心配いりません。
矯正治療によって噛み合わせが改善されると、あごの関節にかかる負担も軽くなります。
ただ、生活習慣やクセ、姿勢、ストレスなどの影響で再びバランスが崩れることもあるのです。
✅顎関節症が再発しやすい要因
- 無意識の食いしばりや歯ぎしり
- 頬杖や横向き寝など、あごに負担をかけるクセ
- スマホやパソコン作業時の姿勢の乱れ
- ストレスによる筋肉の緊張
矯正治療が終わったあとも、「あごをいたわる生活習慣」を意識することが大切です。
正しい噛み合わせを維持するためのメンテナンス
矯正が終わって歯並びがきれいになっても、放っておくと少しずつ元の位置に戻ろうとする性質があります。
これを「後戻り」と呼びますが、それが原因で噛み合わせが崩れると、顎関節にも悪影響が出ることがあります。
✅噛み合わせを安定させるためのポイント
- リテーナー(保定装置)をきちんと使う
→ 治療後すぐは毎日装着が基本。その後は医師の指示に従って徐々に時間を減らします。 - 定期的に歯科でチェックを受ける
→ 噛み合わせのずれやあごの状態を定期的に確認することで、早期の対応が可能です。 - あごに違和感があるときは、我慢せず相談を
→ 早めの対応で、再発や悪化を防げます。
矯正後も顎の健康を保つためのセルフケア
治療が終わっても、日々のケアで顎関節症のリスクをぐっと下げることができます。
難しいことではなく、生活の中で少し意識するだけで変わってきますよ。
✅ご自宅でできるセルフケア例
- リラックスして過ごす時間を作る
ストレスは筋肉を緊張させ、あごに負担をかける原因になります。 - あごのストレッチや軽いマッサージ
お風呂上がりなどに、ゆっくり口を開け閉めする動作を取り入れてみてください。 - 姿勢を見直す
デスクワークやスマホの時間が長い方は、頭が前に出ていないかチェック。あごへの負担が減ります。 - 就寝時のナイトガードの活用(必要な場合)
歯ぎしりがある方は、歯やあごを守るためのマウスピースの使用も検討してみましょう。
矯正治療によって得られた正しい噛み合わせと美しい歯並びを、長く維持するためには、
「治療後のケア」こそがとても重要なステップになります。
9.顎関節症がある人におすすめの矯正方法
 「顎関節症があるけど、矯正治療は受けられるの?」
「顎関節症があるけど、矯正治療は受けられるの?」
「どの装置があごに優しいのか分からない…」
顎関節症の症状があると、矯正治療を始めることに不安を感じている患者様もいらっしゃると思います。
症状に合わせた矯正方法を選べば、あごへの負担を軽くしながら治療を進めることができます。
ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違い
それぞれの矯正装置には、あご関節への影響にも違いがあります。
▶ ワイヤー矯正
- 歯の表面にブラケットをつけ、ワイヤーで力を加えて歯を動かします。
- 微調整が得意で、あごのズレを丁寧にコントロールしやすいのが特長。
- 症状によっては、顎関節のバランスを見ながら、段階的に調整できるのがメリットです。
▶ マウスピース矯正(例:インビザライン)
- 透明なマウスピースを使って、少しずつ歯を動かしていく方法です。
- あごへの圧力がやや弱く、顎関節への負担が少ないといわれています。
- 自由に取り外せるため、顎の動きを制限しすぎないという点も安心材料になります。
💡顎関節症の症状が軽い方や、食いしばりの癖がある方には、マウスピース矯正が向いているケースも多いです。
ただし、重度の噛み合わせの乱れには、ワイヤー矯正の方が適していることもあります。
顎関節症のある患者様に合った矯正の選び方
症状や歯並びの状態によって、「どちらの矯正方法が向いているか」は変わってきます。
大切なのは、“あごの状態をきちんと見たうえで判断する”こと。
✅こんな点に注目して選びましょう
- 口が開きにくい・痛みがある → マウスピース矯正で様子を見るのが安心な場合あり
- あごのズレや噛み合わせのアンバランスが大きい → 精密な調整ができるワイヤー矯正が有効なことも
- 過去に顎関節症が再発している・不安が強い → 顎関節に配慮した矯正プランが必要
いずれの方法を選ぶにしても、しっかりした診断と専門医の判断がカギになります。
顎関節症があるからといって、矯正治療を諦める必要はありません。
むしろ、噛み合わせを整えることで、症状の改善につながる可能性も大いにあるのです。
10.よくある質問
 矯正治療を検討中の患者様からは、顎関節症についてのご相談を多くいただきます。
矯正治療を検討中の患者様からは、顎関節症についてのご相談を多くいただきます。
ここでは、よくあるご質問をまとめて、できるだけわかりやすくお答えします。
Q1.矯正治療をすると顎関節症は治るの?
A1. 噛み合わせのバランスを整えることで、症状が改善するケースもあります。
顎関節症の原因のひとつに「噛み合わせのズレ」があります。
歯並びが整っていないことで、あごに負担がかかり、痛みやカクカク音が出ることがあるのです。
矯正治療によって噛み合わせが安定すると、
- 顎の動きがスムーズになる
- 筋肉の緊張がやわらぐ
- 日常生活でのあごへの負担が減る
などの効果が期待できます。
💡ただし、すべての顎関節症が矯正で治るわけではないため、最初にしっかり診断した上で治療計画を立てることが大切です。
Q2. 矯正中に顎が痛くなったらどうすればいい?
A2. 無理せずすぐにご相談ください。治療内容を調整することで改善できることも多いです。
矯正治療中は、歯やあごに力がかかるため、一時的に顎関節症のような症状が出ることがあります。
- 矯正装置の力が強すぎる
- 歯の動きにあごがついてこられていない
- ストレスや食いしばりが加わっている
といった原因で痛みが出る場合は、装置の調整や生活指導で症状が軽くなることも多いです。
「ちょっと違和感があるな」と感じたら、遠慮なくお知らせくださいね。
Q3. 顎関節症があると矯正治療を受けられない?
A3. 顎関節症があるからといって、矯正治療ができないわけではありません。
むしろ、噛み合わせやあごの使い方を見直すチャンスにもなります。
✅ただし、以下のような点には注意が必要です。
- 症状の強さを見極めること(痛みが強い・口が開かないなど)
- あごの状態をしっかり検査すること(CT・MRI・レントゲンなど)
- 矯正の力加減を調整しながら慎重に進めること
顎関節症の症状がある患者様には、無理のない範囲で進める治療計画を立てますので、ご安心ください。
Q4.顎関節症でもマウスピース矯正はできますか?
A4.はい、可能な場合があります。マウスピース矯正は、取り外しができるという特徴があり、顎関節への負担を調整しやすいというメリットがあります。また、ワイヤー矯正と比べて力のかかり方がやややわらかいため、顎に優しいと感じる患者様もいらっしゃいます。
ただし、マウスピース矯正は症例によっては対応が難しいこともあり、顎の状態によっては別の治療法が適している場合もあります。顎関節症の症状や歯並びの状態をしっかり把握したうえで、無理のない治療法を選ぶことが大切です。
Q5.顎関節症は自然に治ることもあるって本当ですか?
A5.はい、実際に軽度の顎関節症であれば、日常生活で顎に負担をかけないよう注意することで自然に症状が落ち着くこともあります。たとえば、頬杖や片側噛みの癖をやめたり、ストレスによる食いしばりを意識して控えたりするだけで、痛みが和らぐ方もいます。
ただし、症状が長引いたり、悪化していくような場合には、早めに歯科や矯正専門医を受診していただくことをおすすめします。放っておくと、顎関節だけでなく噛み合わせ全体に影響が出る可能性もあるため、自己判断は禁物です。
顎関節症があると「矯正治療はできるの?」「治療して悪化しない?」といった不安を抱える患者様も少なくありません。ですが、矯正治療は顎関節症の原因のひとつである「噛み合わせの乱れ」を改善し、あごの負担を軽減することにもつながります。
もちろん、症状によっては治療の進め方に工夫が必要なケースもありますが、正しい診断と治療計画があれば、顎関節症があっても矯正治療は可能です。
こんなときこそ大切なのは、
- 顎関節の状態をしっかり調べること
- 症状に応じた矯正方法を選ぶこと
- 治療中の変化にも丁寧に対応していくこと
私たちは、患者様の不安やお悩みに寄り添いながら、無理のない安全な矯正治療を心がけています。顎関節症があるからといって、笑顔をあきらめる必要はありません。
「自分にとって本当に合う治療ってなんだろう?」とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。一緒に、お口とあごの健康を守りながら、快適な矯正ライフを目指していきましょう。
————————–
東京都銀座駅の矯正歯科
銀座矯正歯科
〒104-0061
東京都中央区銀座3-3-14
銀座グランディアビルⅡ 6F
☎︎03-3567-5454
————————–
*監修者
*経歴
1998年 富山県立富山中部高等学校卒業。1998~2004年 日本大学松戸歯学部。
2004~2008年 日本大学大学院(歯科矯正学専攻)。
2008~2012年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 助手(専任扱)。
2012~2020年 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 アシスタントドクター。
2013~2014年 ニューヨーク大学CDEP 矯正学修了。
2014~2018年 日本大学松戸歯学部 顎顔面外科学講座 兼任講師。
2014~2015年 カリフォルニア州立大学LA校CDEP 矯正学修了。
2019~2023年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 兼任講師。
2021年~ 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 院長。
2022年~ 一般社団法人日本デジタル矯正歯科学会 理事・学術担当。
2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 クリニカルアドバイザー。
2023年~ Digital Dentistry Society Ambassador (Japan)。
2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 同門会副会長。
2023年~ Ray Face (Ray Dent, Korea) Key Opinion Leader。
*主な所属学会
・日本矯正歯科学会(認定医)
・International Congress of Oral Implantologists (ICOI) インプラント矯正認定医
・Digital Dentistry Society 日本アンバサダー
・先進歯科画像研究会(ADI)歯科用CT認定医
・厚生労働省認定 歯科臨床研修指導医
・日本美容外科学会(JSAPS)関連会員
・Orthopaedia and Solutions マネージャー
・BIODENT 寿谷法コルチコトミーベーシックコース インストラクター
・BIODENT モディファイドコルチコトミーコース インストラクター
・(株)YDM 矯正器材アドバイザー
・ABO Journal Club 主宰
・Cutting Edge of Digital Orthodontics 主宰
*論文・学会発表
- ・加速矯正とアライナー治療による治療期間のコントロール ザ・クインテッセンス2022年11月号
- ・進化するデジタル歯科技術Extra モディファイドコルチコトミー法とSureSmileによる矯正治療 日本歯科評論 81(8)=946:2021.8
- ・進化するデジタル歯科技術 : 3Dプリンターは臨床をどう変革するか(4)矯正治療における3Dプリンターの臨床応用 日本歯科評論 81(4)=942:2021.4
- ・矯正用光重合型レジン系接着システムの接着性能 接着歯学2013年31巻4号P159-166
- ・歯科矯正学における3D診断および治療計画(翻訳)クインテッセンス出版
- ・基礎から学ぶデジタル時代の矯正入門(翻訳統括)クインテッセンス出版
- ・矯正歯科治療のためのコルチコトミー(翻訳)
- ・Effects of compression force on fibroblast growth factor-2 and receptor activator of nuclear factor kappa B ligand production by periodontal ligament cells in vitro. J Periodontal Res. 2008 Apr;43(2):168-73.
- ・Evaluation of the success rate of single- and dual-thread orthodontic miniscrews inserted in the palatal side of the maxillary tuberosity. J World Fed Orthod. 2022 Jun;11(3):69-74.
- ・T-helper 17 cells mediate the osteo/odontoclastogenesis induced by excessive orthodontic forces. Oral Dis. 2012 May;18(4):375-88.
- IL-8 and MCP-1 induced by excessive orthodontic force mediates odontoclastogenesis in periodontal tissues. Oral Dis. 2011 Jul;17(5):489-98.
- ・Effects of HSP70 on the compression force-induced TNF-α and RANKL expression in human periodontal ligament cells. Inflamm Res. 2011 Feb;60(2):187-94.
- ・Effects of relaxin on collagen type I released by stretched human periodontal ligament cells. Orthod Craniofac Res. 2009 Nov;12(4):282-8.
- ・Levels of RANKL and OPG in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement and effect of compression force on releases from periodontal ligament cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.
詳しいプロフィールはこちらより