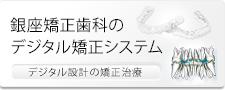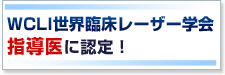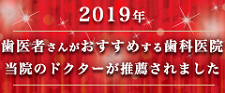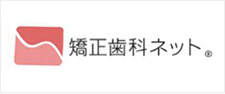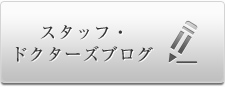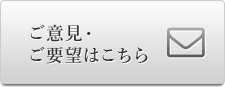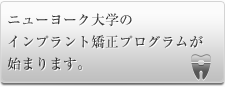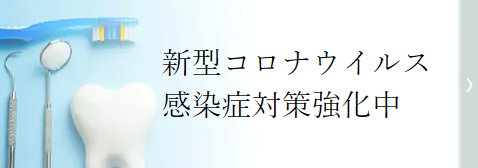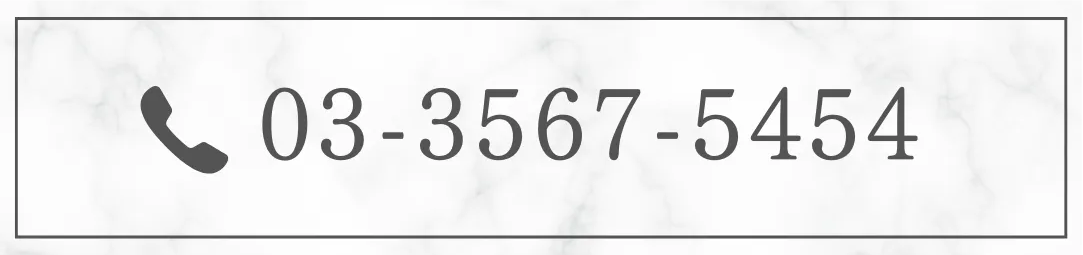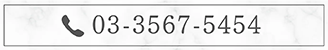こんにちは。銀座矯正歯科です。
姿勢の乱れが歯並びや噛み合わせに大きな影響を与えることがあるのはご存知でしょうか。猫背や頬杖、足を組むクセなど、日常の何気ない姿勢の乱れが、顎のズレや噛み合わせのバランスを崩し、歯並びの乱れにつながってしまうことも。
反対に、正しい姿勢を保つことは、歯並びやお口の健康を守る大切な一歩。矯正治療だけでなく、普段の姿勢や生活習慣を見直すことも、美しい歯並びと健やかな体づくりにつながります。
今回は、姿勢が歯並びに与える影響や、予防・改善のためにできることをご紹介していきます。歯の美しさと体のバランス、どちらも大切にしたい方は、ぜひチェックしてみてください。
1.こんなお悩みありませんか?
 ・長時間のデスクワークでつい猫背になってしまう
・長時間のデスクワークでつい猫背になってしまう- ・口を閉じるのが苦手で、気づくといつも口呼吸になっている
- ・最近、顎が疲れやすかったり、噛み合わせに違和感を感じることがある
もし、こうしたお悩みにひとつでも当てはまるなら、それは「姿勢」が歯並びや噛み合わせに影響を与えているサインかもしれません。
実は、「姿勢」と「歯並び」は見た目以上に深くつながっていて、気づかないうちにお互いに影響を及ぼし合っていることがあります。たとえば、猫背の姿勢が続くと、頭の位置が前に出て顎の関節に負担がかかり、噛み合わせがズレてくることもあります。
この記事では、姿勢が歯並びや噛み合わせに与える影響と、その改善方法について、できるだけわかりやすくご紹介していきます。毎日のちょっとした意識が、歯や顎の健康を守る第一歩になるかもしれません。
2.姿勢と歯並びの深い関係とは?
 パッと聞くと無関係に思えるかもしれませんが、姿勢と歯並びの関係は、とても密接です。姿勢が悪いまま過ごしていると、気づかないうちに歯並びや噛み合わせ、さらには顎の関節にまで影響を及ぼしてしまうことがあります。
パッと聞くと無関係に思えるかもしれませんが、姿勢と歯並びの関係は、とても密接です。姿勢が悪いまま過ごしていると、気づかないうちに歯並びや噛み合わせ、さらには顎の関節にまで影響を及ぼしてしまうことがあります。
姿勢が悪いと歯並びが乱れる理由
長時間スマホを見たり、デスクワークで前かがみの姿勢が続いたりすると、頭の位置が前に出て首や顎に負担がかかります。この状態が続くと、顎の位置がズレてしまい、噛み合わせにもゆがみが生じることがあります。
その結果、歯が正しく並ぶスペースが圧迫されたり、片側だけに力がかかって歯が傾いたりするなど、歯列全体に影響が出てくることも。
特に以下のような生活習慣がある方は注意が必要です。
- ・長時間のデスクワークで猫背気味
- ・スマホやタブレットを下向きで見る時間が長い
- ・座るときに足を組むクセがある
- ・片方の肩や首ばかり凝る
✅このような姿勢のクセが、気づかぬうちに歯並びや噛み合わせの乱れにつながっている可能性があります。
噛み合わせと体のバランスはつながっている
噛み合わせは、歯だけの問題ではありません。顎の動き、首の位置、肩や背中の筋肉のバランスといった“全身の連動”が深く関係しています。
たとえば、
- ・噛み合わせにズレがあると体の重心が崩れ、姿勢が悪くなる
- ・姿勢が悪いと顎の位置がズレ、歯や噛み合わせに悪影響が出る
といった具合に、歯と体のバランスはお互いに影響し合っています。
姿勢を整えることで歯の健康も守れる
正しい姿勢を保つことで、歯や顎にかかる余計な負担が減り、噛み合わせの安定にもつながります。矯正治療で歯並びを整えても、姿勢が乱れたままだと後戻りのリスクも高くなってしまいます。
以下のような簡単な心がけで、歯並びの安定や顎の健康維持につながります。
- ・椅子に座るときは骨盤を立て、背筋を伸ばす
- ・スマホはなるべく顔の高さに持ち上げて見る
- ・こまめに首や肩を動かして緊張をほぐす
- ・鏡で左右の肩や耳の高さをチェックしてみる
歯並びを整えることは、単に「見た目がきれいになる」だけではありません。姿勢の改善や全身のバランスにも深く関わっています。日常の姿勢を見直すことは、矯正治療の効果をより長く保つための大切なポイントでもあります。
3.悪い姿勢がもたらす歯並びへの影響
 毎日の姿勢が、歯並びや噛み合わせに関係していることをご存じでしょうか?
毎日の姿勢が、歯並びや噛み合わせに関係していることをご存じでしょうか?
実は、無意識にとっている姿勢やクセが、あごの位置を変えたり、歯に余計な力をかけたりして、歯並びに影響を与えていることがあります。
猫背が歯並びに与える負担とは?
猫背の姿勢は、見た目の問題だけでなく、歯やあごにも思わぬ負担をかけています。
背中が丸まり、頭が前に出ると、首やあごの位置がズレてしまい、以下のような影響が出ることがあります。
- ・下あごが後ろに押し込まれて、噛み合わせが浅くなる
- ・前歯に過剰な力がかかり、出っ歯気味になることがある
- ・顎関節への負担が増えて、痛みや開けづらさの原因になることも
猫背の姿勢が習慣化すると、成長期のお子様ではあごの発育に影響を与え、大人でも噛み合わせのズレを引き起こすことがあります。
特に長時間スマホやパソコンを使っている方は、知らず知らずのうちに猫背になりやすいので注意が必要です。
片方の頬杖が噛み合わせをズラす?
テレビを見ているときや仕事中など、無意識に「頬杖」をついている方も多いのではないでしょうか。
中でも片側だけに力をかける頬杖は、あごのバランスを大きく崩す原因になります。
✅こんなリスクがあります:
- ・あごが一方向に押されて、噛み合わせが左右どちらかにズレてしまう
- ・歯の位置が少しずつ動き、ゆがんだ歯並びになることがある
- ・顔の輪郭や表情筋にも偏りが出る可能性がある
特に成長途中のお子様では、こうしたクセが骨格に影響しやすく、将来的な歯列不正の原因になることもあります。
大人でも、頬杖のクセが続けば、矯正治療中の歯の動きにも悪影響を与えることがあります。
足を組むクセが歯並びにも悪影響を及ぼす
「足を組むクセがあるけど、関係あるの?」と驚かれることもありますが、足を組むことで骨盤や背骨がゆがみ、姿勢が不安定になります。
この姿勢の崩れが、間接的にあごの位置や噛み合わせに影響を及ぼすのです。
✅具体的には:
- ・骨盤のゆがみ → 背骨のねじれ → 頭の傾き → あごのズレ
- ・左右の噛む力のバランスが崩れ、特定の歯にだけ力がかかる
- ・あごのズレから、歯列の片寄りや歯ぎしり、食いしばりにつながることも
座っているときの足の組み方や重心のかけ方は、歯並びに直接は関係ないように見えて、実は全身のバランスを通じて深くつながっています。長時間のデスクワークをされる方や、片足に体重をかけるクセのある方は要注意です。
悪い姿勢や何気ないクセが、知らないうちに歯並びを崩してしまうことがあります。
矯正治療で歯を整えても、日常生活で不自然な姿勢を続けていると、再び噛み合わせが乱れてしまうこともあります。
4.口呼吸と姿勢の意外な関係
 「いつの間にか口が開いてしまう」「寝ているときに口呼吸になっている気がする」
「いつの間にか口が開いてしまう」「寝ているときに口呼吸になっている気がする」
そしてこの“口呼吸”、単にお口のクセではなく、姿勢と深く関係していることをご存じでしょうか?
口呼吸の原因は姿勢の悪さから?
口呼吸は「クセ」や「鼻づまり」のせいと思われがちですが、悪い姿勢が根本原因になっていることもあります。
特に猫背や前かがみの姿勢を続けていると、あごの位置が後ろに下がり、舌が正常な位置(上あご)に収まらなくなります。
✅その結果…
- ・舌が下がることで、口がポカンと開きやすくなる
- ・鼻呼吸がしづらくなり、自然と口呼吸に
- ・肩や首の筋肉も緊張し、呼吸自体が浅くなる傾向に
長時間のスマホ操作やデスクワーク、ゲームなどで前かがみになる習慣がある方は、特に注意が必要です。
姿勢の悪さが、知らず知らずのうちに呼吸の仕方まで変えてしまっているかもしれません。
口を閉じる力と正しい姿勢の重要性
本来、私たちがリラックスしているときは「唇が自然に閉じて、鼻で呼吸をしている」状態が理想的です。
しかし、姿勢が崩れていると、口を閉じるための筋肉がうまく使えなくなります。
✅特に関係しているのが以下の筋肉です:
- ・口輪筋(こうりんきん):唇を閉じる筋肉
- ・舌筋(ぜっきん):舌を支える筋肉
- ・頬筋(きょうきん):頬の内側から口まわりを支える筋肉
これらは姿勢が崩れることで機能が弱まりやすく、結果的に「口を閉じていられない」状態を招きます。
正しい姿勢をキープすることで、これらの筋肉がしっかり働き、自然と口が閉じやすくなるのです。
口呼吸が歯並びに与えるリスクとは?
口呼吸を続けていると、お口まわりのバランスが崩れ、歯並びやあごの成長にも影響を及ぼします。
特に成長期のお子様では、次のようなリスクが高くなります。
✅口呼吸による主なリスク
- ・出っ歯や開咬(前歯が閉じない状態)になりやすい
- ・あごの発育が不十分で、顔が長くなる傾向がある
- ・口内が乾燥しやすく、むし歯や歯周病のリスクが高まる
- ・舌の位置が下がることで、歯が内側から押されず、きれいに並ばない
- ・噛む力や飲み込む力が弱まり、正しい咀嚼ができなくなる
大人の患者様でも、口呼吸が続くことで口内トラブルや歯並びの後戻りなどにつながる可能性があります。
口呼吸の予防や改善には、まず姿勢を見直すことが第一歩です。以下のことを意識してみましょう。
5.噛み合わせのズレと体の歪み
 「歯並びと肩こりって関係あるんですか?」
「歯並びと肩こりって関係あるんですか?」
「噛み合わせが悪いと、体の不調が起こるって聞いたけど本当?」
お口の中の状態が、実は全身のバランスや健康にまで影響している。今回はそんな“噛み合わせと体のつながり”についてお話ししていきます。
噛み合わせが悪いと全身のバランスも崩れる?
歯並びが乱れていたり、上下の歯がしっかり噛み合っていない状態を「噛み合わせが悪い」といいます。
この噛み合わせのズレが、あごの動きだけでなく、体の姿勢や筋肉の使い方にまで影響を及ぼしていることがあります。
✅噛み合わせの乱れが起こす影響には以下のようなものがあります:
- ・片側ばかりで噛むクセがつき、左右の筋肉のバランスが崩れる
- ・あごのズレが首や肩の位置にも影響し、猫背や首の傾きにつながる
- ・体全体がゆがみやすくなり、骨盤や背骨のねじれの原因になる
つまり、お口の中の「ちょっとしたズレ」が、やがて全身のバランスを崩してしまうこともあるんです。
頭痛・肩こり・腰痛の原因が歯並びの乱れ?
慢性的な頭痛や肩こり、腰の違和感など、病院で検査してもはっきりした原因が見つからない不調。
実はこうした「原因不明の体の不調」に、噛み合わせが関係しているケースもあります。
たとえば…
- ・噛むたびに筋肉が片側だけ使われ、首や肩がこわばる
- ・あごを正しい位置に保てないことで、首の筋肉が常に緊張状態に
- ・体のバランスが崩れ、腰や背中に余計な負担がかかる
こういった状態が続くと、慢性的な不調として現れてきます。
ご自身では気づかないうちに、「歯並びの乱れ=姿勢の乱れ=体の不調」のサイクルにはまっていることもあるのです。
体の不調を改善するための歯列矯正
「歯並びと関係あるなんて思わなかったけど、もしかして…」と感じた患者様へ。
そんなときは、歯列矯正という選択肢を考えてみてもいいかもしれません。
歯列矯正では、単に歯をきれいに並べるだけでなく、噛み合わせのバランスを整えることをとても大切にしています。
このバランスが整うことで、以下のような変化が期待できます。
✅矯正治療による体へのメリット
- ・噛む筋肉の左右差が減り、あごや肩の力みがやわらぐ
- ・あごの位置が整い、姿勢もまっすぐになりやすい
- ・長年悩んでいた頭痛や肩こりの軽減につながるケースも
- ・しっかり噛めることで、消化吸収の効率が上がり、全身の代謝も安定する
もちろん、すべての体の不調が歯並びのせいとは限りません。
ただ、長年の症状が「なかなか改善しない」と感じている患者様には、お口の中を見直してみることが大切です。
歯は、噛むためだけのものではありません。
全身とつながっているからこそ、お口の中のケアが、体全体の健康にもつながっていくんです。
6.正しい姿勢で歯並びを守るための習慣
 歯並びというと、「生まれつきだから仕方ない」と思われることもありますが、実は日々の姿勢や習慣が大きく関係しています。
歯並びというと、「生まれつきだから仕方ない」と思われることもありますが、実は日々の姿勢や習慣が大きく関係しています。
日常生活の中で少し意識を変えるだけでも、歯並びやあごの健康を守ることができます。
デスクワーク中の姿勢改善ポイント
仕事や勉強などで長時間座ることが多い方は、姿勢のクセが歯並びや噛み合わせに影響しているかもしれません。
✅悪い姿勢の例:
- ・背中が丸まって猫背になっている
- ・頭が前に出て、あごが引っ込んでいる
- ・片側に体重をかけて座っている(足を組んだり、身体をねじるなど)
このような姿勢が続くと、あごの位置がズレたり、噛み合わせに左右差が出てしまいます。
💡改善のポイント:
- ・椅子には深く腰掛け、背筋を伸ばす
- ・両足は床にしっかりつけて、足を組まない
- ・モニターの高さは目線と同じか少し下に設定する
- ・肘は90度に保ち、肩の力を抜いてリラックス
- ・定期的に立ち上がってストレッチをする
姿勢を整えることで、あごへの負担が減り、歯並びにも良い影響を与えます。
スマホの使い方で歯並びを守るコツ
スマホを見る時間が増えると、自然と首が前に出て、頭が下がった“スマホ首”の姿勢になりがちです。この姿勢は、あごや首に負担をかけ、結果として歯並びの乱れにつながることも。
✅よくある悪い使い方:
- ・スマホを膝の上で操作し、顔が大きく下を向いている
- ・うつ伏せでスマホを見ながら頬杖をついている
- ・就寝前、横向きでスマホを見るクセがある
💡歯並びを守るコツ:
- ・スマホはできるだけ顔の高さに持ち上げて操作する
- ・長時間見続けないよう、1時間に1回は目を休める
- ・横向きではなく、仰向けや正面から見る姿勢を意識する
- ・頬杖を避けて、左右均等に顔の筋肉を使うよう心がける
ちょっとした意識の積み重ねが、将来のあごや歯並びを守ってくれます。
仰向け寝で歯並びと顎関節を守る
寝ているときの姿勢も、歯並びやあごの位置に影響を与えます。特にうつ伏せや横向きの姿勢は、あごを圧迫しやすく、噛み合わせがズレる原因になりかねません。
✅注意したい寝方:
- ・うつ伏せ寝:顔の片側に強く圧がかかり、あごのゆがみや歯列のズレにつながる
- ・横向き寝:片側だけに体重がかかり、顎関節への負担が偏る
💡理想的な寝方:
- ・仰向けで寝ることで、あごや顔全体にかかる力が均等になる
- ・枕の高さは、首と肩のラインが自然になる程度に調整
- ・硬すぎず柔らかすぎないマットレスを使って、姿勢を安定させる
夜間の寝姿勢は無意識の時間ですが、習慣づけることで歯並びや顎関節を守ることができます。
矯正治療を検討されている患者様や、すでに治療中の患者様にとって、正しい姿勢はとても大切なサポートになります。
7.歯並びを守るためのエクササイズ
 歯並びをきれいに保つには、矯正治療だけでなく、毎日の生活習慣やセルフケアもとても大切です。
歯並びをきれいに保つには、矯正治療だけでなく、毎日の生活習慣やセルフケアもとても大切です。
その中でも今回は、歯並びに影響を与える「姿勢」と「あご周りの筋肉」を意識した簡単なエクササイズをご紹介します。
自宅でもすぐにできる内容なので、ぜひ毎日の習慣に取り入れてみてください。
顎周りの筋肉を鍛える簡単ストレッチ
歯並びを整えるためには、歯を支えているあごや口周りの筋肉がしっかり働いていることが大切です。
特に「口輪筋(こうりんきん)」や「舌の筋肉」は、歯並びや噛み合わせに直結します。
- 唇を閉じるトレーニング「む〜体操」
【やり方】
- ①背筋を伸ばして座る
- ②唇をしっかり閉じて、「むー」と声を出さずに5秒キープ
- ③5回繰り返す
💡ポイント:唇の周りの筋肉がピリッとする感覚があればOKです。
- 舌の位置を整える「ベロ上げ運動」
【やり方】
- ①口を閉じたまま、舌の先を上あごの前歯の裏側につける
- ②舌全体を上あごに吸いつけるようにキープ(5秒)
- ③これを5回繰り返す
💡ポイント:舌が自然に上にある状態が、理想的な歯並びを支えます。
姿勢を整えるための正しいストレッチ方法
姿勢の悪さがあごや歯並びに影響することは、これまでの章でもお伝えしてきました。
ここでは、特に首・肩・背中を意識した、簡単にできるストレッチを2つご紹介します。
- 首まわしストレッチ
【やり方】
- ①背筋を伸ばして座る or 立つ
- ②ゆっくりと首を前・横・後ろに回す(左右3回ずつ)
💡ポイント:無理に力を入れず、深呼吸しながら行うのがコツです。
- 肩甲骨はがしストレッチ
【やり方】
- ①両手を後ろで組み、胸を開く
- ②肩甲骨をギュッと寄せるようにして5秒キープ
- ③ゆっくり戻して、5回繰り返す
💡ポイント:スマホやパソコン作業で前かがみになった肩まわりをリセットできます。
日常生活で取り入れやすい姿勢改善のポイント
エクササイズとあわせて、普段の生活の中で姿勢を整える意識を持つことで、歯並びを守る効果がさらにアップします。
✅毎日の中でできること
- ・座るときは、深く腰掛けて背筋を伸ばす
→ 背中を丸めないだけで、あごの位置が安定します。 - ・スマホやPCの画面は目の高さに
→ 下を向く時間が減り、あごへの負担が軽くなります。 - ・両足をしっかり床につけて、足を組まない
→ 骨盤のゆがみを防ぎ、体全体のバランスが整います。 - ・寝るときは仰向けがベスト
→ あごや顔に余計な力がかからず、左右バランスのよい歯並びに。
継続がカギ!歯並びと全身の健康を守るために
今回ご紹介したエクササイズや姿勢改善は、どれも短時間でできる簡単なものばかりです。
でも、一番大切なのは「毎日少しずつ続けること」。習慣にすることで、歯並びはもちろん、あごや体のゆがみ予防にもつながります。
✅こんな方におすすめ
- ・矯正治療中で、歯並びの安定を保ちたい患者様
- ・口が開きやすく、口呼吸のクセがある患者様
- ・姿勢の悪さや肩こりが気になっている患者様
- ・成長期のお子様の歯並びを守りたい保護者様
どれか一つでも当てはまる方は、ぜひ今日から試してみてくださいね。
矯正治療は、歯を動かすだけでなく、その後の安定を保つことがとても大切です。
歯並びが乱れる原因を減らすためにも、体のバランスや筋肉の状態を整えておくことはとても効果的です。
8.矯正治療が姿勢にもたらすメリット
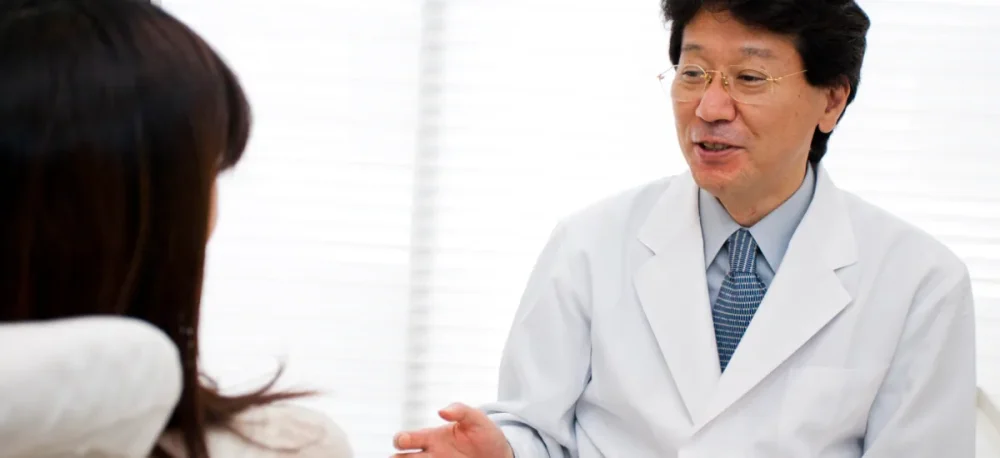 矯正治療を受けることで、見た目の美しさだけでなく、噛み合わせや体のバランスが整い、全身の健康にも良い影響があることが分かってきています。
矯正治療を受けることで、見た目の美しさだけでなく、噛み合わせや体のバランスが整い、全身の健康にも良い影響があることが分かってきています。
噛み合わせを改善することで姿勢も整う
私たちの体は、歯・あご・首・背中・腰といった各部位がバランスを取りながら支え合っています。
その中で「噛み合わせ」は、あごの位置を決める大事なポイント。
噛み合わせがズレていると、体全体の軸もズレてしまいやすくなります。
✅噛み合わせのズレが引き起こす悪循環:
- ・下あごの位置が左右どちらかに偏る
- ・首や肩の筋肉に片側だけ負担がかかる
- ・姿勢が傾いたり、猫背になったりする
- ・腰や膝への負担も大きくなる
矯正治療によって噛み合わせが正しい位置に整うと、あごが自然なポジションに戻り、そこから首・肩・背骨までのバランスも整いやすくなります。
矯正治療がもたらす全身の健康効果
歯並びや噛み合わせの改善が、体にとってどれほど良い影響を与えるのか、あまり知られていないかもしれません。
でも、次のような全身の健康効果が期待できます。
✅矯正治療による健康メリット:
- ・肩こり・首こりの軽減
→ 噛み合わせが安定すると、左右の筋肉のバランスも改善され、緊張がやわらぎます。 - ・頭痛の頻度が減ることも
→ あごのズレがなくなることで、周辺の神経や筋肉への圧迫が減少。 - ・姿勢改善による疲れにくい体づくり
→ 骨格が整うことで、体の使い方が楽になります。 - ・睡眠の質が上がるケースも
→ 呼吸がしやすくなり、口呼吸やいびきの改善につながることもあります。 - ・スポーツや運動時のパフォーマンス向上
→ 正しい噛み合わせでしっかり噛むことができ、筋力やバランス感覚にも好影響。
見た目の改善だけでなく、体全体が元気になるサポートとして矯正治療を受ける方も増えてきています。
矯正後の正しい姿勢をキープするポイント
矯正治療で整った歯並びと体のバランスを長く保つためには、治療後の姿勢や生活習慣もとても大切です。
✅姿勢を整えるために意識したいこと:
- ・デスクワーク中は背筋を伸ばして、足を床につける
- ・スマホやパソコンの画面は目線の高さに合わせる
- ・寝るときは仰向けの姿勢が理想的。枕の高さも調整
- ・片方ばかりで噛まないように意識する
- ・頬杖や足組みなど、無意識のクセに注意する
姿勢を整えるだけで、あごへの負担が減り、歯並びの安定にもつながります。
また、矯正後に装着するリテーナー(保定装置)も、歯の後戻りを防ぐために欠かせません。
しっかり使いながら、正しい姿勢を保つ意識を持ち続けていきましょう。
矯正治療というと「歯をきれいに整えるためのもの」というイメージが強いかもしれませんが、実は体のゆがみや姿勢の改善、全身の健康にも深く関わっている治療です。
9.子どもの頃から意識すべき姿勢と歯並びの関係
 「うちの子、歯並びが気になって…でも矯正はまだ早いのかな?」
「うちの子、歯並びが気になって…でも矯正はまだ早いのかな?」
実は、矯正治療を始めるタイミングだけでなく、日頃の姿勢やクセが、お子様の歯並びに大きな影響を与えているんです。
成長期の体はまだやわらかく変化しやすいため、ちょっとした習慣や姿勢が、歯並びやあごの発育に直結します。
成長期の姿勢が歯並びに与える影響
子どもの頃は、あごや歯の成長が活発な時期です。
この時期に正しい姿勢が身についていれば、自然と歯やあごのバランスも整いやすくなります。
しかし、姿勢が悪い状態が続くと、次のような影響が出やすくなります。
✅姿勢の乱れが引き起こす影響:
- ・頭が前に出ると、下あごが後ろに引っ込みやすくなり、噛み合わせにズレが出る
- ・背中が丸まることで、舌の位置が下がり、口呼吸のクセがつきやすくなる
- ・あごの成長に偏りが生じ、顔の左右バランスが崩れる
つまり、良い姿勢は「見た目のきれいさ」だけでなく、あごの発育や歯の並びにも大きく関わっているということです。
子どもの頃のクセがもたらすリスク
大人に比べて、子どもは無意識のクセが出やすい時期です。
その中でも特に気をつけたいのが以下のような習慣です。
✅よく見られるクセとその影響:
- ・頬杖
→ 片側のあごだけに力が加わり、左右のバランスが崩れます。 - ・口呼吸
→ 口が開きっぱなしになり、舌が下がり、前歯が出やすくなります(出っ歯傾向)。 - ・猫背
→ あごの位置が後ろにズレ、噛み合わせに悪影響。あごの成長が制限されることも。 - ・指しゃぶりや舌癖(舌を前に出すクセ)
→ 開咬(前歯が閉じない)や出っ歯の原因になります。
こうしたクセは、気づかないうちに歯やあごに負担をかけてしまうため、早めの対処がとても大切です。
正しい姿勢を習慣化するためのポイント
無理なくお子様に正しい姿勢を習慣づけるためのポイントをご紹介します。
✅姿勢改善のための工夫:
- ・机と椅子の高さを見直す
→ 足が床につく高さに調整し、背もたれにしっかりもたれて座れる環境に。 - ・タブレットやスマホは目線の高さで使わせる
→ 画面を下に置かず、できるだけ顔を正面に向けた姿勢を。 - ・食事中は「口を閉じてよく噛む」習慣を意識
→ 唇を閉じて噛むことで、口周りや舌の筋肉も鍛えられます。 - ・寝る姿勢も大切!仰向けが基本
→ 横向きやうつ伏せで寝ると、あごや歯に片寄った力がかかります。 - ・姿勢を「褒める」習慣を
→ 「今の姿勢いいね!」とポジティブな声かけで、子どもも意識しやすくなります。
毎日少しずつ意識づけをすることで、正しい姿勢が自然と身についていきます。
子どもの頃の「ちょっとした姿勢やクセ」が、大人になってからの歯並びやあごのバランスに影響することがあります。
だからこそ、小さいうちからできるケアや意識づけが大切です。
正しい姿勢と生活習慣をサポートすることで、お子様の健やかな成長と、きれいな歯並びの基礎をつくることができます。
10.よくある質問
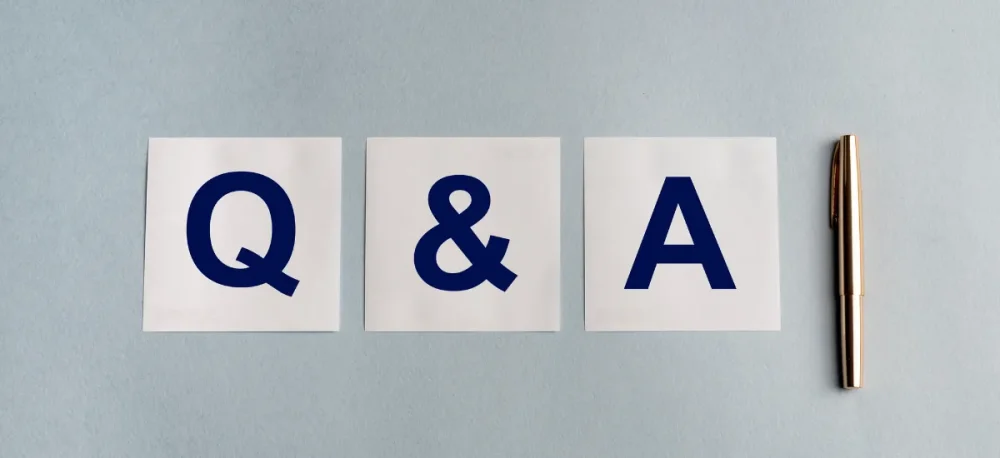 一見まったく別のことのように思える“歯並び”と“姿勢”ですが、実は深いつながりがあるんです。
一見まったく別のことのように思える“歯並び”と“姿勢”ですが、実は深いつながりがあるんです。
今回は、患者様からよくいただく疑問を取り上げながらお答えしていきます。
Q1:姿勢を改善すると歯並びも変わる?
A1:すぐに歯が動くわけではありませんが、間接的にはとても関係があります。
姿勢が悪いと、あごの位置や筋肉の使い方に影響が出て、長い目で見ると歯並びの乱れにつながることがあります。
✅姿勢が歯並びに与える影響:
- ・猫背になると下あごが後ろに引っ込んで噛み合わせが不安定になる
- ・頬杖や足組みなどのクセが片方のあごに力をかけ、左右のバランスが崩れる
- ・舌の位置が下がって口呼吸が習慣化し、歯並びに影響するケースも
特に成長期のお子様は、骨格がまだやわらかく変化しやすい時期なので、正しい姿勢を保つことが将来の歯並びを守ることにもつながります。
Q2:矯正治療は姿勢の悪さにも効果がある?
A2:直接「姿勢を治す」わけではありませんが、結果的に姿勢改善につながることもあります。
矯正治療によって噛み合わせが整うと、あごの位置や筋肉の使い方が安定し、それが体のバランスに良い影響を与えることがあります。
✅矯正治療が間接的に姿勢に与える効果:
- ・噛むときに左右均等な力がかかるようになり、首や肩の筋肉の負担が減る
- ・あごの正しい位置が保たれることで、頭の重さを首と背中でしっかり支えられるようになる
- ・噛み合わせのズレがなくなると、全身の軸もブレにくくなる
患者様の中には、矯正治療後に「肩こりが減った」「姿勢が良くなったと周りに言われた」と感じる方もいらっしゃいます。
もちろんすべての方に当てはまるわけではありませんが、お口まわりの安定は体全体の安定にもつながると考えています。
Q3:どのタイミングで矯正を始めるのがベスト?
A3:患者様の状態によって異なりますが、「気になったときが始めどき」です。
矯正治療には、年齢やタイミングに応じてさまざまな方法があります。
✅子どもの場合(5歳〜12歳くらい):
- ・骨格の成長を活かした「早期矯正」が可能
- ・あごのバランスを整えながら歯の土台を作れるため、将来的な抜歯の可能性を減らせることも
- ・姿勢のクセや呼吸のクセもこの時期に直しやすい
✅大人の場合(中高生〜成人):
- ・永久歯が生え揃っていれば、いつでも矯正治療はスタート可能
- ・目立ちにくい装置(マウスピース型矯正など)も豊富に選べる
- ・姿勢や体の使い方のクセが定着していることも多いため、生活習慣の見直しと合わせて取り組むのが効果的
どのタイミングであっても、「まず相談してみること」がとても大切です。
矯正を始めることで、歯並びはもちろん、あごや姿勢、体のバランスまで整っていく可能性があります。
歯並びは、見た目だけでなく、噛む・話す・呼吸するといった日常の動きや、体全体のバランスとも深く関係しています。
そして、その土台となるのが「姿勢」や「日々のクセ」です。
矯正治療を通して歯並びを整えることはもちろん大切ですが、治療の効果を長く保ち、より良い状態をキープしていくには、日常生活の中でのちょっとした意識がとても大きな力になります。
「最近猫背気味かも」「片方でばかり噛んでいる気がする」
そんな小さな気づきが、将来のきれいな歯並びや健康なあごを守る第一歩です。
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
————————–
東京都銀座駅の矯正歯科
銀座矯正歯科
〒104-0061
東京都中央区銀座3-3-14
銀座グランディアビルⅡ 6F
☎︎03-3567-5454
————————–
*監修者
*経歴
1998年 富山県立富山中部高等学校卒業。1998~2004年 日本大学松戸歯学部。
2004~2008年 日本大学大学院(歯科矯正学専攻)。
2008~2012年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 助手(専任扱)。
2012~2020年 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 アシスタントドクター。
2013~2014年 ニューヨーク大学CDEP 矯正学修了。
2014~2018年 日本大学松戸歯学部 顎顔面外科学講座 兼任講師。
2014~2015年 カリフォルニア州立大学LA校CDEP 矯正学修了。
2019~2023年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 兼任講師。
2021年~ 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 院長。
2022年~ 一般社団法人日本デジタル矯正歯科学会 理事・学術担当。
2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 クリニカルアドバイザー。
2023年~ Digital Dentistry Society Ambassador (Japan)。
2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 同門会副会長。
2023年~ Ray Face (Ray Dent, Korea) Key Opinion Leader。
*主な所属学会
・日本矯正歯科学会(認定医)
・International Congress of Oral Implantologists (ICOI) インプラント矯正認定医
・Digital Dentistry Society 日本アンバサダー
・先進歯科画像研究会(ADI)歯科用CT認定医
・厚生労働省認定 歯科臨床研修指導医
・日本美容外科学会(JSAPS)関連会員
・Orthopaedia and Solutions マネージャー
・BIODENT 寿谷法コルチコトミーベーシックコース インストラクター
・BIODENT モディファイドコルチコトミーコース インストラクター
・(株)YDM 矯正器材アドバイザー
・ABO Journal Club 主宰
・Cutting Edge of Digital Orthodontics 主宰
*論文・学会発表
- ・加速矯正とアライナー治療による治療期間のコントロール ザ・クインテッセンス2022年11月号
- ・進化するデジタル歯科技術Extra モディファイドコルチコトミー法とSureSmileによる矯正治療 日本歯科評論 81(8)=946:2021.8
- ・進化するデジタル歯科技術 : 3Dプリンターは臨床をどう変革するか(4)矯正治療における3Dプリンターの臨床応用 日本歯科評論 81(4)=942:2021.4
- ・矯正用光重合型レジン系接着システムの接着性能 接着歯学2013年31巻4号P159-166
- ・歯科矯正学における3D診断および治療計画(翻訳)クインテッセンス出版
- ・基礎から学ぶデジタル時代の矯正入門(翻訳統括)クインテッセンス出版
- ・矯正歯科治療のためのコルチコトミー(翻訳)
- ・Effects of compression force on fibroblast growth factor-2 and receptor activator of nuclear factor kappa B ligand production by periodontal ligament cells in vitro. J Periodontal Res. 2008 Apr;43(2):168-73.
- ・Evaluation of the success rate of single- and dual-thread orthodontic miniscrews inserted in the palatal side of the maxillary tuberosity. J World Fed Orthod. 2022 Jun;11(3):69-74.
- ・T-helper 17 cells mediate the osteo/odontoclastogenesis induced by excessive orthodontic forces. Oral Dis. 2012 May;18(4):375-88.
- IL-8 and MCP-1 induced by excessive orthodontic force mediates odontoclastogenesis in periodontal tissues. Oral Dis. 2011 Jul;17(5):489-98.
- ・Effects of HSP70 on the compression force-induced TNF-α and RANKL expression in human periodontal ligament cells. Inflamm Res. 2011 Feb;60(2):187-94.
- ・Effects of relaxin on collagen type I released by stretched human periodontal ligament cells. Orthod Craniofac Res. 2009 Nov;12(4):282-8.
- ・Levels of RANKL and OPG in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement and effect of compression force on releases from periodontal ligament cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.
詳しいプロフィールはこちらより