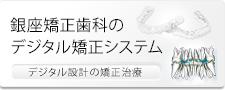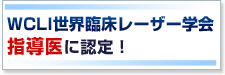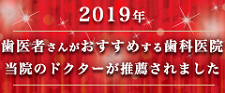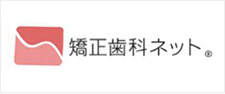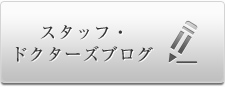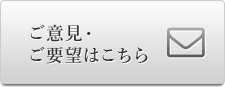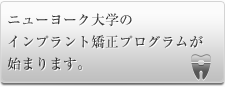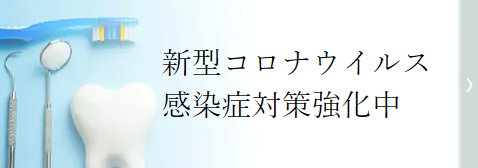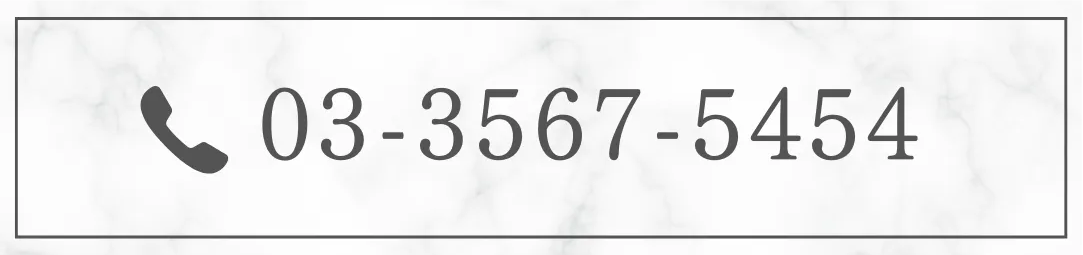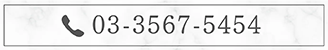こんにちは。銀座矯正歯科です。
「矯正を始めてから、冷たい飲み物を飲むとズキッとする…」矯正治療中に歯がしみるのは決して珍しいことではありません。特に、ワイヤー矯正やマウスピース矯正を始めたばかりの時期や、調整を行った後に「知覚過敏」のような症状を感じる方は多くいます。
しかし、「これって虫歯?」「矯正が原因?」「治療を続けて大丈夫?」と、不安になるのも当然です。矯正治療中の知覚過敏にはいくつかの原因があり、適切なセルフケアや歯科での対処を行うことで、症状を軽減することができます。
今回は、矯正治療中に歯がしみる原因や、しみるタイミング、効果的なセルフケア、歯科医院での対処法について解説していきます。
矯正治療を快適に続けるために、まずは「なぜ歯がしみるのか?」を知ることから始めましょう!
1.こんなお悩みありませんか?
 矯正治療を始めてから、「歯がしみる」と感じることはありませんか?矯正を進めている患者様の中には、以下のような症状でお悩みの方も多くいらっしゃいます。
矯正治療を始めてから、「歯がしみる」と感じることはありませんか?矯正を進めている患者様の中には、以下のような症状でお悩みの方も多くいらっしゃいます。
- ・矯正を始めてから歯がしみるようになった
- ・冷たいものや熱いものを口にするとズキッとする
- ・矯正のワイヤーやマウスピースが原因なのか不安
- ・虫歯ではないのに痛みを感じる
これらの症状は、矯正治療中によく見られる反応のひとつです。矯正装置をつけたことで、歯や歯ぐきに負担がかかり、歯がしみやすくなることがあります。特に、歯の動きが活発な治療初期や、装置を調整した直後に感じやすい症状です。
「虫歯じゃないのに歯がしみるのはなぜ?」と不安に思う方も多いですが、これは矯正による一時的な影響である場合がほとんどです。
2.矯正治療中に歯がしみるのはなぜ?
 矯正治療を始めてから、冷たい飲み物や熱い食べ物を口にすると「ズキッ!」と痛みを感じることはありませんか?このような症状は「知覚過敏」と呼ばれるもので、矯正治療中に起こることがあります。では、なぜ矯正中に歯がしみるのでしょうか?
矯正治療を始めてから、冷たい飲み物や熱い食べ物を口にすると「ズキッ!」と痛みを感じることはありませんか?このような症状は「知覚過敏」と呼ばれるもので、矯正治療中に起こることがあります。では、なぜ矯正中に歯がしみるのでしょうか?
知覚過敏とは?その仕組みを解説
知覚過敏は、歯のエナメル質が削れたり、歯ぐきが下がることで象牙質が露出し、神経に刺激が伝わりやすくなる状態のことをいいます。象牙質には無数の細い管(象牙細管)があり、そこを刺激が伝わることで痛みを感じます。
一般的な知覚過敏の原因
- ✅過度なブラッシング(強い力で磨きすぎる)
- ✅歯ぎしりや食いしばり(エナメル質をすり減らす)
- ✅歯ぐきが下がる(加齢や歯周病によるもの)
- ✅酸性の食品や飲料の摂取(エナメル質を弱くする)
矯正治療が知覚過敏を引き起こす理由
矯正治療中に歯がしみる原因として、次のようなことが考えられます。
- ✔歯が動くことで神経が刺激される
- 矯正治療では、ワイヤーやマウスピースを使って歯を動かします。その際、歯の根元にある神経が刺激され、一時的に敏感になりやすくなります。
- 特に、矯正を始めたばかりの頃や装置を調整した直後にこの症状を感じやすいです。
- ✔歯ぐきが下がりやすくなる
- 矯正によって歯が移動することで、歯ぐきの位置が変化し、一時的に下がることがあります。
- 歯ぐきが下がると象牙質が露出し、知覚過敏が起こることがあります。
- ✔矯正装置の影響で歯みがきが難しくなる
- 矯正装置がついていると、歯の表面が磨きにくくなり、歯垢や汚れがたまりやすくなることがあります。
- その結果、歯ぐきが炎症を起こしやすくなり、知覚過敏が悪化する可能性があります。
虫歯との違いを見分けるポイント
「歯がしみると虫歯かも?」と心配になる方もいるかもしれません。知覚過敏と虫歯の違いを見分けるポイントを押さえておきましょう。
|
症状 |
知覚過敏 |
虫歯 |
|
痛みのタイミング |
刺激があったとき(冷たい・熱いもの、甘いもの) |
何もしなくても痛むことがある |
|
痛みの継続時間 |
一時的(数秒で消える) |
持続的(じわじわ痛むことが多い) |
|
見た目の変化 |
歯に目立った変色や穴はない |
黒ずみや穴があることが多い |
|
原因 |
矯正による刺激、歯ぐきの下がり |
虫歯菌による歯の破壊 |
もし、「何もしなくてもズキズキ痛む」「特定の歯だけが強く痛い」という場合は、虫歯の可能性があるので、歯科医院でチェックを受けることをおすすめします。
矯正治療中に歯がしみるのは、知覚過敏による一時的な症状であることが多いです。歯の動きや歯ぐきの変化が原因となるため、多くの場合は時間が経つにつれて落ち着いてきます。
3.矯正治療中に知覚過敏が起こりやすいタイミング
 矯正治療中に「急に歯がしみるようになった!」と感じることはありませんか?知覚過敏の症状が出やすいタイミングはいくつかあり、特に矯正装置をつけた直後や歯の動きが活発な時期に起こりやすいです。
矯正治療中に「急に歯がしみるようになった!」と感じることはありませんか?知覚過敏の症状が出やすいタイミングはいくつかあり、特に矯正装置をつけた直後や歯の動きが活発な時期に起こりやすいです。
矯正装置をつけた直後にしみることがある?
矯正治療を始めたばかりの患者様から「装置をつけた翌日から歯がしみるようになった」という相談を受けることがあります。これは、矯正装置によって歯に力がかかり、神経が一時的に敏感になっているためです。
矯正治療では、歯に持続的な力を加えることでゆっくりと移動させるため、歯の根元や神経に刺激が加わります。すると、歯の内部の組織が反応し、しみるような違和感を感じることがあります。この症状は通常1〜2週間程度で落ち着くことがほとんどです。
知覚過敏を感じやすいタイミング
- ✅矯正装置(ワイヤーやマウスピース)をつけた直後
- ✅ゴムかけやワイヤーの調整後
- ✅矯正装置を外した直後(リテーナー装着時)
特に、矯正治療を始めたばかりの時期や、歯が急に動き始める段階では、一時的に痛みやしみる症状が出やすい傾向にあります。
歯が動く過程で知覚過敏になるメカニズム
矯正治療では、歯を少しずつ正しい位置に移動させるため、歯の根元にある歯根膜(しこんまく)という組織が圧迫されたり引っ張られたりします。これにより、歯の神経が刺激され、一時的に敏感になり、知覚過敏が起こることがあります。
歯が動くときに知覚過敏が起こる理由
- ✔歯根膜の圧迫
- 矯正の力によって、歯の根元の組織が圧迫されると、神経が刺激を受けやすくなり、冷たいものや甘いものがしみることがあります。
- ✔象牙質の露出
- 矯正中に歯ぐきの位置が変わることで、エナメル質の内側にある象牙質(ぞうげしつ)が露出することがあります。象牙質には細い管(象牙細管)があり、ここを通じて刺激が神経に伝わるため、しみる症状が出ることがあります。
- ✔歯ぐきの変化
- 矯正治療によって歯が動くことで、歯ぐきの位置が変わり、根元の部分が一時的に敏感になることがあります。
このように、歯が動く過程で神経が一時的に敏感になることが、矯正治療中の知覚過敏の主な原因といえます。
歯のやすりがけ(IPR)後にしみやすくなる理由
矯正治療では、歯をスムーズに動かすためにIPR(Interproximal Reduction/ストリッピング)と呼ばれる処置を行うことがあります。これは、歯の表面をわずかに削ってスペースを作る方法です。
IPRを行うことで知覚過敏が起こる理由
- ✅エナメル質が一部削れるため、象牙質が露出しやすくなる
- ✅削られた部分が一時的に敏感になり、冷たいものや熱いものがしみることがある
- ✅処置後すぐはしみやすいが、多くの場合、数週間で落ち着く
IPR後に知覚過敏が気になる場合は、知覚過敏用の歯みがき粉を使ったり、歯科医院でフッ素コーティングをしてもらうことで症状が和らぐことが多いです。
矯正治療中に知覚過敏が起こるのは、歯が動くことで神経が刺激されたり、歯ぐきの位置が変わったりするためです。特に、装置をつけた直後やワイヤーの調整後、IPR(歯のやすりがけ)後などに症状が出やすい傾向にあります。
この症状は一時的なもので、ほとんどの場合、時間が経てば落ち着いていきます。しかし、症状が長く続く場合や、強い痛みを感じる場合は、歯科医師に相談することをおすすめします。
4.どんな人が矯正中に歯がしみやすい?
 矯正治療を受けると、誰もが少なからず歯の違和感を感じることがありますが、中でも「歯がしみる」症状が出やすい方には特定の特徴があります。もし、以下の項目に当てはまる場合は、事前に対策をしておくことで症状を和らげることができます。
矯正治療を受けると、誰もが少なからず歯の違和感を感じることがありますが、中でも「歯がしみる」症状が出やすい方には特定の特徴があります。もし、以下の項目に当てはまる場合は、事前に対策をしておくことで症状を和らげることができます。
歯茎が下がりやすい方(歯周病・加齢)
矯正治療によって歯の位置が変わると、歯茎の高さが変化することがあります。特に、もともと歯茎が下がりやすい方は、矯正の影響で象牙質(歯の内部にある神経に近い部分)が露出しやすくなるため、しみる症状が起こることがあります。
歯茎が下がる原因
- ✔歯周病の影響
- 歯周病が進行すると、歯茎が後退し、歯の根元が露出してしまいます。
- その状態で矯正治療を行うと、さらにしみやすくなることがあります。
- ✔加齢による歯茎の変化
- 年齢とともに歯茎のボリュームが減り、自然と歯の根元が露出しやすくなります。
- ✔矯正装置による影響
- 矯正装置のワイヤーやマウスピースが歯茎に当たり、軽度の炎症を引き起こすことがあります。
- これが原因で歯茎が少し下がり、知覚過敏が起こることがあります。
📌対策
- 歯周病の治療を先に行う
- 歯茎の健康状態を整えてから矯正を始めることで、歯がしみるリスクを軽減できます。
- 歯茎の保護を意識したブラッシング
- 歯茎を傷つけないよう、やわらかめの歯ブラシを使いましょう。
歯ブラシの圧が強すぎる方
「しっかり磨かないと汚れが落ちない」と思い、ついゴシゴシ強く歯を磨いてしまう方も、矯正中に歯がしみやすい傾向があります。力を入れすぎるとエナメル質が削れ、象牙質が露出しやすくなるため、冷たいものがしみる原因になります。
磨きすぎによる影響
- ✔エナメル質が薄くなり、知覚過敏が悪化
- 矯正治療で歯が動くと、歯の表面が敏感になります。
- その状態で強く磨きすぎると、エナメル質が薄くなり、さらにしみる原因に。
- ✔歯ぐきが傷つき、下がることで象牙質が露出
- 矯正装置があることで歯茎が炎症を起こしやすくなります。
- そこに強いブラッシングが加わると、歯茎がダメージを受けやすくなり、知覚過敏につながります。
📌対策
- 歯磨きの力加減をチェックする
- 歯ブラシを持つときは、鉛筆を持つような軽い力で握りましょう。
- 力の入れすぎを防ぐために電動歯ブラシを活用するのもおすすめです。
- 知覚過敏用の歯磨き粉を使用
- フッ素や硝酸カリウムが配合された歯磨き粉を使うことで、神経への刺激をブロックし、しみる症状を緩和できます。
以前から知覚過敏の症状があった方
もともと知覚過敏の症状があった方は、矯正治療によってその症状が悪化しやすい傾向があります。
知覚過敏が起こりやすい歯の特徴
- ✔歯ぎしり・食いしばりがある
- 強い力がかかることで歯の表面に小さなヒビが入り、しみやすくなります。
- ✔エナメル質が薄い
- 生まれつきエナメル質が薄い方や、ホワイトニングを頻繁に行っていた方は、矯正中にしみやすい可能性があります。
- ✔むし歯治療で詰め物が多い
- 以前のむし歯治療で詰め物がある歯は、矯正の動きによって違和感を感じることがあります。
📌対策
- ナイトガードを活用する
- 歯ぎしりや食いしばりがある方は、矯正中でもナイトガードを使うことで知覚過敏の悪化を防ぐことができます。
- 歯科医院でフッ素塗布をしてもらう
- フッ素には、エナメル質を強化する効果があり、歯のしみる症状を抑えるのに役立ちます。
矯正治療中に歯がしみやすい方には、以下の特徴があります。
✔ 歯茎が下がりやすい(歯周病・加齢)
✔ 強く歯を磨きすぎる
✔ もともと知覚過敏の症状があった
これらの要因によって、矯正治療中に歯の神経が刺激を受けやすくなり、知覚過敏が発生することがあります。
しかし、適切なケアを行うことで、知覚過敏の症状を和らげることは可能です。特に、優しいブラッシング、フッ素の活用、ナイトガードの使用などを取り入れることで、しみる症状を軽減できます。
5.矯正治療中の知覚過敏を防ぐセルフケア
 矯正治療中に歯がしみる症状を抑えるためには、毎日のセルフケアがとても重要です。正しいケアを行うことで、知覚過敏の症状を軽減し、快適に矯正治療を進めることができます。
矯正治療中に歯がしみる症状を抑えるためには、毎日のセルフケアがとても重要です。正しいケアを行うことで、知覚過敏の症状を軽減し、快適に矯正治療を進めることができます。
知覚過敏用歯磨き粉の選び方と使い方
矯正中に歯がしみる場合は、知覚過敏専用の歯磨き粉を使用することで、症状を和らげることができます。
知覚過敏用歯磨き粉の選び方
以下の成分が含まれている歯磨き粉を選ぶと、知覚過敏の緩和に役立ちます。
- ✔硝酸カリウム:
- 神経の過敏な反応を抑え、しみる症状を軽減。
- ✔フッ化ナトリウム(フッ素):
- エナメル質を強化し、歯をしみにくくする。
- ✔ヒドロキシアパタイト:
- エナメル質の修復を助け、象牙質の露出を防ぐ。
知覚過敏用歯磨き粉の使い方
- 毎日継続して使用する
- 効果を実感するには、最低でも2週間以上続けることが大切です。
- 歯磨き後、すぐに口をゆすがない
- 成分を歯に留めるため、すすぎは少量の水で1回程度にとどめましょう。
力を入れすぎない正しい歯磨きのコツ
矯正装置が付いていると、歯に汚れがたまりやすくなり、「しっかり磨かなければ」と思うあまり、強い力でブラッシングしてしまう方も多いです。しかし、強く磨きすぎるとエナメル質が削れ、象牙質が露出しやすくなるため、知覚過敏の原因となります。
正しい歯磨きの方法
✅やわらかめの歯ブラシを使う
✅鉛筆を持つように軽い力でブラッシングする
✅歯の表面を優しくなでるように磨く
✅矯正装置の周りは歯間ブラシやワンタフトブラシを活用
▶ おすすめのブラッシング方法
- 矯正中の歯磨きには、「小刻みに優しく動かす」ことがポイントです。
- ワイヤー矯正の方は、歯と歯茎の境目を45度の角度で磨くと効果的です。
- マウスピース矯正の方は、装置を外した後に丁寧に歯磨きをすることが大切です。
刺激を避けるための食事の工夫
知覚過敏があると、食事の際にしみることがあり、食事が楽しめなくなることも。歯に負担をかけない食べ方を意識することで、知覚過敏の症状を和らげることができます。
避けるべき食べ物
- ・冷たいもの
- アイスクリーム、氷、冷えた飲み物(冷たい水やジュース)
- ・熱すぎるもの
- 熱いコーヒー、熱々のスープ
- ・酸性の強い食べ物
- 柑橘類(レモン・グレープフルーツ)、酢の物、炭酸飲料
- ・硬い食べ物
- 硬いおせんべい、ナッツ類
おすすめの食べ方
- ✔温度差の少ない食べ物を選ぶ
- ぬるめのスープや常温の飲み物を意識する。
- ✔ゆっくり噛んで食べる
- しみる歯に刺激を与えないように、奥歯でゆっくり咀嚼する。
- ✔ストローを活用する
- 冷たい飲み物を飲むときは、前歯に直接触れないようストローを使うとしみるのを防げます。
矯正治療中に知覚過敏を防ぐためには、毎日のセルフケアがとても重要です。「矯正治療中に歯がしみる」と感じても、適切なセルフケアを行えば症状を和らげることが可能です。矯正治療をスムーズに進めるためにも、日々のケアを見直してみましょう!
6.知覚過敏の症状が強い場合の対処法
 矯正治療中に知覚過敏の症状が強く出ると、日常生活に影響が出てしまうこともあります。特に、食事や歯磨きのたびにズキッとした痛みを感じる場合は、適切なケアや治療を受けることが大切です。
矯正治療中に知覚過敏の症状が強く出ると、日常生活に影響が出てしまうこともあります。特に、食事や歯磨きのたびにズキッとした痛みを感じる場合は、適切なケアや治療を受けることが大切です。
歯科医院でできる「しみ止め」の処置とは?
歯科医院では、知覚過敏の症状を抑えるための専用の処置が可能です。しみる症状がひどい場合は、早めに相談することをおすすめします。
歯科医院でできる知覚過敏の治療法
✅ フッ素塗布(フッ化ナトリウム塗布)
→ フッ素を歯に塗布し、エナメル質を強化することで知覚過敏を軽減します。
✅グルタルアルデヒド塗布
→ 歯の表面にある象牙細管(知覚過敏の原因となる微細な管)を封鎖し、刺激が伝わらないようにします。
✅レーザー治療
→ レーザーを照射して知覚過敏の症状を軽減する方法。痛みが少なく、即効性があるのが特徴です。
✅歯の詰め物(コンポジットレジン)による保護
→ 歯の表面をコーティングすることで、刺激を遮断し、しみる症状を抑えます。
特に矯正治療中は、歯が動くことで一時的に知覚過敏が起こることが多いですが、これらの処置を受けることで痛みを大幅に軽減できる可能性があります。
コーティング剤を使った歯の保護方法
知覚過敏用のコーティング剤を使用することで、しみる症状を抑えることができます。歯科医院で処方されるものもあれば、市販で購入できるタイプもあります。
おすすめのコーティング剤と使用方法
✅歯科医院で処方される「シールド剤」
→ 歯の表面に塗ることで、象牙質の露出を防ぎ、知覚過敏を軽減します。
✅市販の知覚過敏ケア用ジェル
→ フッ素配合のジェルを使用することで、エナメル質を強化し、刺激を受けにくくします。
✅デンタルシーラント(歯の表面保護剤)
→ 歯の表面に薄い膜を作り、冷たい飲み物や食べ物による刺激を防ぎます。
📌 ポイント
- これらのコーティング剤は、歯磨きの後に塗布し、しばらく放置することで効果が出ます。
- 定期的に使用することで、知覚過敏の症状を軽減できるため、継続してケアすることが大切です。
症状が長引く場合の追加治療オプション
矯正治療中の知覚過敏は、多くの場合一時的なものですが、長期間続く場合は他の原因がある可能性も考えられます。
追加の治療オプション
✅象牙質の再石灰化治療
→ エナメル質が薄くなっている場合、カルシウムやリン酸を補給することで、再石灰化を促進し、象牙質の露出を防ぎます。
✅歯の詰め物の調整
→ 矯正中に噛み合わせが変わることで一部の歯に負担がかかりすぎることがあります。その場合、詰め物を調整することで負担を減らし、知覚過敏を和らげます。
✅根管治療(神経の処置)
→ まれに、歯の神経が過敏になりすぎている場合は、根管治療を行うことで症状を改善できます。
📌 注意点
- 知覚過敏の症状が 数ヶ月以上続く 場合は、虫歯や歯周病の可能性 も考えられるため、歯科医院でのチェックを受けることが重要 です。
- 強い痛みがある場合 は、矯正装置の調整が必要なケースもあるため、すぐに担当の歯科医師に相談しましょう。
矯正治療中に知覚過敏の症状が強く出た場合は、早めに適切な対策を取ることが重要 です。矯正治療は、美しい歯並びと健康な噛み合わせを手に入れるための大切なステップですが、途中で起こるトラブルにも適切に対処することで、快適に治療を続けることができます。
7.矯正装置の種類による影響はある?
 矯正治療中に歯がしみる原因の一つに、「矯正装置の種類」が関係していることがあります。ワイヤー矯正、マウスピース矯正、裏側矯正(舌側矯正)など、装置のタイプによって知覚過敏のリスクや症状の出方が異なる ため、どのような違いがあるのか解説します。
矯正治療中に歯がしみる原因の一つに、「矯正装置の種類」が関係していることがあります。ワイヤー矯正、マウスピース矯正、裏側矯正(舌側矯正)など、装置のタイプによって知覚過敏のリスクや症状の出方が異なる ため、どのような違いがあるのか解説します。
ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違い
矯正装置のタイプによって、知覚過敏が起こる頻度や症状の強さが異なります。それぞれの特徴を理解しておくことで、症状を軽減する工夫ができます。
① ワイヤー矯正の場合
✅ 歯に一定の圧力がかかるため、一時的に知覚過敏を感じることがある
✅装置の調整後(ワイヤーを締めた後)にしみる症状が出やすい
✅矯正用のブラケット周りに汚れが溜まりやすく、歯の表面が弱くなることがある
ワイヤー矯正は、歯を動かす力が強いため、歯の根に圧力がかかりやすく、それが原因で知覚過敏の症状が出る ことがあります。特に調整後は、食べ物や飲み物の刺激を敏感に感じることがあるため、知覚過敏用の歯磨き粉を使う などの対策をとることが重要です。
② マウスピース矯正の場合
✅ 歯をゆっくり動かすため、知覚過敏の症状が出にくい
✅歯全体をカバーするため、外部からの刺激を受けにくい
✅装置の取り外しができるため、歯磨きがしやすく、汚れによる知覚過敏リスクが低い
マウスピース矯正(インビザラインなど)は、歯を少しずつ動かすため、ワイヤー矯正に比べて知覚過敏が起こる頻度は少ないとされています。ただし、装置を外した直後は歯が敏感になりやすいため、冷たい飲み物や酸性の食べ物を避ける といった工夫が必要です。
裏側矯正(舌側矯正)特有のリスクは?
裏側矯正(舌側矯正)は、歯の裏側に装置をつけるため、見た目が気にならない というメリットがあります。しかし、知覚過敏のリスクに関しては、ワイヤー矯正と同じような注意が必要です。
✅舌に装置が当たるため、歯磨きがしにくく、プラークが溜まりやすい
✅ワイヤー矯正と同様に、装置の調整後に歯がしみることがある
✅歯の裏側が常に装置に触れているため、唾液の流れが変わり、口腔内のpHバランスが崩れやすい
📌 対策
- 矯正用の小さめの歯ブラシを使い、歯の裏側をしっかり磨く
- 知覚過敏用の歯磨き粉 を使用し、エナメル質を守る
- 矯正装置の違和感が強い場合は、担当の歯科医師に相談して装置の微調整を行う
知覚過敏になりにくい装置の選び方
矯正治療中に知覚過敏のリスクを最小限に抑えたい場合は、装置選びも重要なポイントになります。装置の選択肢と、それぞれの特徴を比較してみましょう。
知覚過敏のリスクが低い矯正装置
|
矯正装置の種類 |
知覚過敏リスク |
特徴 |
|
マウスピース矯正 |
低い |
歯全体をカバーし、外部刺激を防ぐ |
|
ワイヤー矯正(表側) |
中程度 |
ワイヤーの調整後にしみることがある |
|
裏側矯正(舌側矯正) |
やや高い |
歯磨きが難しく、歯の裏側にプラークが溜まりやすい |
✅知覚過敏が心配な方は、マウスピース矯正を選ぶとリスクが低い
✅ワイヤー矯正を希望する場合は、知覚過敏用の歯磨き粉やフッ素ケアを取り入れる ことで症状を抑えることが可能
矯正治療中の知覚過敏の症状は、装置の種類によってリスクの程度が異なる ことが分かります。矯正装置の選び方によって、知覚過敏の影響を減らすことができるため、治療前に歯科医師と相談し、自分に合った装置を選ぶ ことが大切です。
8.矯正治療中の歯茎下がりと知覚過敏の関係
 矯正治療を進める中で、「歯茎が下がった気がする」「歯が長く見えるようになった」と感じることはありませんか?これは、矯正による歯の移動が原因で歯茎が下がる ことがあるためです。さらに、歯茎が下がると知覚過敏になりやすくなる ため、適切なケアが必要になります。
矯正治療を進める中で、「歯茎が下がった気がする」「歯が長く見えるようになった」と感じることはありませんか?これは、矯正による歯の移動が原因で歯茎が下がる ことがあるためです。さらに、歯茎が下がると知覚過敏になりやすくなる ため、適切なケアが必要になります。
矯正によって歯茎が下がることはある?
矯正治療では、歯を理想的な位置に動かす ことが目的ですが、その際に歯を支えている歯槽骨(しそうこつ)や歯茎にも影響 が及びます。歯の移動によって、歯茎が一時的に下がることがあるのです。
✅歯茎が下がりやすいケース
- 歯の根が外側に傾いた場合 → 特に前歯が外側に広がると、歯茎が薄くなり、後退しやすい
- もともと歯茎が薄い方 → 歯茎の厚みが少ないと、移動時の負担で後退しやすい
- 歯周病の影響がある場合 → 歯を支える骨が弱っていると、歯茎も下がりやすい
また、矯正装置によって歯茎に炎症が起こると、腫れたり下がったりすることもあります。そのため、歯茎の健康を守るためのケアが重要 です。
歯茎が下がると知覚過敏になりやすい理由
歯茎が下がると、通常は歯茎に覆われている象牙質(ぞうげしつ) という部分が露出してしまいます。この象牙質は、エナメル質よりも柔らかく、刺激を感じやすい構造になっている ため、冷たいものや熱いものがしみる ようになるのです。
✅知覚過敏が起こるメカニズム
- 歯茎が下がる → 歯の根元が露出する
- 象牙細管(ぞうげさいかん)がむき出しになる → 内部の神経に刺激が伝わりやすくなる
- 冷たいもの・熱いものがしみる → 知覚過敏の症状が出る
特に、矯正治療によって歯が移動する過程で歯茎が下がった場合、知覚過敏の症状が強く出ることがある ため、注意が必要です。
歯茎を健康に保つためのケア方法
歯茎の健康を守ることは、知覚過敏の予防にもつながります。矯正治療中でもできるケア方法をチェックして、歯茎のトラブルを防ぎましょう。
①正しい歯磨きを心がける
✅歯茎にやさしいブラッシング を意識する
✅柔らかめの歯ブラシを使用する
✅電動歯ブラシを使う場合は圧をかけすぎない
矯正装置があると、つい力を入れてゴシゴシ磨きたくなりますが、強く磨くと歯茎が傷ついて後退の原因になる ため、やさしく丁寧にブラッシングすることが大切です。
②フッ素入りの歯磨き粉を使う
✅フッ素は歯の表面を強化し、象牙質を保護する効果がある
✅知覚過敏用の歯磨き粉(硝酸カリウム配合)も有効
知覚過敏用の歯磨き粉には、刺激をブロックする成分 が含まれているものがあるため、症状が気になる場合は歯科医院でおすすめの歯磨き粉を相談する のもよいでしょう。
③歯茎マッサージを取り入れる
✅歯茎の血流を促進し、健康な状態を維持する
✅指や柔らかめの歯ブラシでやさしくマッサージ
歯茎マッサージは、歯茎の血行を良くし、歯槽骨を健康に保つための効果があります。矯正治療中でも簡単にできるので、歯磨きの際に軽くマッサージする習慣をつける のがおすすめです。
④矯正中の定期検診を受ける
✅ 歯科医院で歯茎の状態をチェックしてもらう
✅必要に応じて歯茎のケアや追加の処置を受ける
歯茎が下がる前に、定期的に歯科医師に診てもらうことが大切 です。必要に応じて歯茎のコーティング処置 を行ったり、知覚過敏が悪化しないように早めに対応 することができます。
矯正治療中に歯茎が下がると、知覚過敏のリスクが高くなる ことがあります。しかし、適切なケアを行えば、歯茎を健康に保ち、知覚過敏の症状を抑えることが可能です。
9.矯正治療を続けながら知覚過敏を改善する方法
 矯正治療中に歯がしみると、「このまま矯正を続けて大丈夫なの?」と不安になることもありますよね。しかし、知覚過敏の症状があるからといって、矯正を中断する必要はありません。適切な対処をすれば、矯正治療を続けながら快適に過ごすことができます。
矯正治療中に歯がしみると、「このまま矯正を続けて大丈夫なの?」と不安になることもありますよね。しかし、知覚過敏の症状があるからといって、矯正を中断する必要はありません。適切な対処をすれば、矯正治療を続けながら快適に過ごすことができます。
一時的な症状?それとも治療が必要?
知覚過敏には 一時的なもの と 治療が必要なもの があります。まずは、自分の症状がどちらなのかを確認しましょう。
✅一時的な知覚過敏の特徴
- 矯正装置をつけた直後にしみる
- 数日~1週間で症状が軽くなる
- 歯の移動による圧力が原因
✅治療が必要な知覚過敏の特徴
- しみる症状が数週間以上続く
- 冷たいものだけでなく、温かいものでもしみる
- しみるだけでなく、ズキズキとした痛みを感じる
しみる症状が長引いたり、痛みが強くなった場合は、虫歯や歯のトラブルが隠れている可能性がある ため、早めに歯科医師に相談しましょう。
しみるからといって矯正を中断しないために
「歯がしみるのがつらくて、矯正治療を中断しようか迷っている」という方もいるかもしれません。しかし、矯正を途中でやめると、歯並びが元の位置に戻ってしまう(後戻り) リスクがあります。
矯正治療を中断せずに快適に続けるためには、以下のポイントを意識しましょう。
✅知覚過敏用の歯磨き粉を使用する
→ 硝酸カリウム や フッ素 を含む歯磨き粉を使うことで、歯の神経を守りながら症状を和らげることができます。
✅歯を冷やしすぎたり熱すぎるものを避ける
→ 冷たいアイスや熱々のスープなどは、一時的にしみる症状を悪化させることがあるため、症状が落ち着くまで控えましょう。
✅力を入れすぎず、やさしく歯磨きをする
→ 強くゴシゴシ磨くと、歯の表面のエナメル質が削れて知覚過敏が悪化する ことがあります。
✅歯科医院で「しみ止め」の処置を受ける
→ フッ素塗布や、コーティング剤を塗布することで、象牙質を保護し、知覚過敏の症状を和らげることができます。
知覚過敏があるからといって矯正をやめる必要はありません。適切なケアを続けることで、矯正治療を快適に進めることができます!
矯正治療をしながら快適に過ごすためのポイント
矯正中の知覚過敏を改善しながら、できるだけ快適に過ごすためのポイントをまとめました。
①毎日のケアを見直す
✅歯磨きの圧を調整し、やさしくブラッシングする
✅知覚過敏用の歯磨き粉を活用する
✅フッ素を取り入れ、歯を強化する
②食事に気をつける
✅ 冷たいもの・熱いものを避ける
✅酸っぱいもの(柑橘類、炭酸飲料など)を控える → 酸がエナメル質を溶かしやすくする
✅繊維質の多い食べ物を意識して食べる → 噛む回数が増えると唾液の分泌が促進され、知覚過敏を和らげる効果が期待できる
③矯正装置の影響を最小限にする
✅ワイヤー矯正の場合 → 歯の移動の影響を受けやすいため、歯科医師と相談しながら進める
✅マウスピース矯正の場合 → 歯に均一な力がかかるため、知覚過敏の影響が比較的少ない
④定期的に歯科医院でチェックを受ける
✅症状がひどい場合は早めに相談する
✅知覚過敏の進行を防ぐために、定期的なフッ素塗布を受ける
✅矯正の進行状況を確認し、歯の負担を調整してもらう
矯正治療中に知覚過敏を感じることは珍しくありませんが、適切なケアをすれば、矯正を中断することなく快適に続けることができます。
10.よくある質問
 矯正治療中に歯がしみる症状が出ると、「これはいつまで続くの?」「矯正が終われば治るの?」と不安になることもありますよね。ここでは、矯正治療中の知覚過敏に関するよくある質問にお答えしながら、症状を和らげるためのポイントをご紹介します。
矯正治療中に歯がしみる症状が出ると、「これはいつまで続くの?」「矯正が終われば治るの?」と不安になることもありますよね。ここでは、矯正治療中の知覚過敏に関するよくある質問にお答えしながら、症状を和らげるためのポイントをご紹介します。
Q1.知覚過敏は治る?矯正が終わればなくなる?
A1.矯正が終われば改善することがほとんどです。
矯正治療による知覚過敏は、歯の移動や装置の影響で一時的に起こるケースが多いです。そのため、矯正が完了して歯が安定すれば、自然に症状が落ち着くことがほとんど です。
ただし、次のようなケースでは、矯正が終わった後も知覚過敏が続く可能性があります。
✔ 歯茎が下がった場合 → 矯正中に歯茎が後退してしまうと、歯の根元が露出し、知覚過敏が長引くことがあります。
✔ エナメル質が削れてしまった場合 → 強いブラッシングや歯ぎしりなどが原因で、エナメル質が薄くなっていると、矯正後も症状が続くことがあります。
知覚過敏の原因によっては、矯正終了後にフッ素塗布やコーティング剤で保護する治療を行うことで、症状を軽減できることが多いです。
Q2.知覚過敏になりにくい歯磨き粉の成分とは?
A2.知覚過敏を和らげるためには、歯磨き粉の選び方が重要です。 市販の歯磨き粉にはさまざまな種類がありますが、以下の成分が含まれているものを選ぶと効果的 です。
✔ 硝酸カリウム(カリウムイオン)
→ 歯の神経を保護し、痛みの伝達をブロックする働きがあります。
✔ フッ素(フッ化ナトリウム)
→ エナメル質を強化し、酸に強い歯を作ります。知覚過敏だけでなく虫歯予防にも◎
✔ 乳酸アルミニウム
→ 象牙質の表面をコーティングし、刺激をブロックする効果 があります。
✔ ハイドロキシアパタイト
→ エナメル質の修復をサポートし、知覚過敏を和らげる働き があります。
📌 避けた方がよい成分
❌ 研磨剤(シリカなどが含まれるもの) → 研磨力が強すぎると、エナメル質を削ってしまい、知覚過敏が悪化することがあります。
❌ 発泡剤(ラウリル硫酸ナトリウムなど) → 泡立ちがよすぎると、短時間で歯磨きを終えてしまい、汚れがしっかり落とせないことがあります。
矯正治療中は歯のケアがより重要になるため、歯科医師と相談しながら自分に合った歯磨き粉を選ぶと安心 です。
Q3.一時的なもの?それとも放置すると悪化する?
A3.一時的な知覚過敏なら問題ありませんが、長引く場合は要注意です。
✔ 一時的な知覚過敏の特徴
- 矯正装置をつけた直後 や 歯が移動しているとき にしみる
- 数日~1週間程度で症状が落ち着く
- 知覚過敏用の歯磨き粉を使うと改善する
このような症状であれば、矯正治療が進むにつれて自然に落ち着くことが多いです。
✔ 悪化する可能性がある知覚過敏の特徴
- 冷たいものだけでなく、温かいものでもしみる
- 歯ブラシの刺激や、甘いものを食べたときにもしみる
- 症状が数週間以上続く、または悪化している
この場合、虫歯や歯茎の後退、エナメル質の損傷などが原因となっている可能性があります。 そのまま放置すると、知覚過敏が悪化したり、歯の健康に影響を与えることもあるため、早めに歯科医院で相談しましょう。
矯正治療中に歯がしみる症状は、多くの患者様が経験するものです。これは、歯が動く過程で神経が一時的に敏感になったり、歯茎が下がることで象牙質が露出するために起こることが主な原因です。しかし、適切なケアを行うことで、この症状を軽減し、快適に矯正治療を続けることが可能です。
矯正治療は、美しい歯並びと正しい噛み合わせを手に入れるための大切なプロセスです。途中で「歯がしみる…」と感じることがあっても、適切な対処をすることで快適に治療を進めることができます。症状が気になる場合は、我慢せずに歯科医師に相談することをおすすめします。
矯正治療をスムーズに進めるために、毎日のセルフケアと適切な対処を心がけましょう!
————————–
東京都銀座駅の矯正歯科
銀座矯正歯科
〒104-0061
東京都中央区銀座3-3-14
銀座グランディアビルⅡ 6F
☎︎03-3567-5454
————————–
*監修者
*経歴
1998年 富山県立富山中部高等学校卒業。1998~2004年 日本大学松戸歯学部。
2004~2008年 日本大学大学院(歯科矯正学専攻)。
2008~2012年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 助手(専任扱)。
2012~2020年 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 アシスタントドクター。
2013~2014年 ニューヨーク大学CDEP 矯正学修了。
2014~2018年 日本大学松戸歯学部 顎顔面外科学講座 兼任講師。
2014~2015年 カリフォルニア州立大学LA校CDEP 矯正学修了。
2019~2023年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 兼任講師。
2021年~ 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 院長。
2022年~ 一般社団法人日本デジタル矯正歯科学会 理事・学術担当。
2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 クリニカルアドバイザー。
2023年~ Digital Dentistry Society Ambassador (Japan)。
2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 同門会副会長。
2023年~ Ray Face (Ray Dent, Korea) Key Opinion Leader。
*主な所属学会
・日本矯正歯科学会(認定医)
・International Congress of Oral Implantologists (ICOI) インプラント矯正認定医
・Digital Dentistry Society 日本アンバサダー
・先進歯科画像研究会(ADI)歯科用CT認定医
・厚生労働省認定 歯科臨床研修指導医
・日本美容外科学会(JSAPS)関連会員
・Orthopaedia and Solutions マネージャー
・BIODENT 寿谷法コルチコトミーベーシックコース インストラクター
・BIODENT モディファイドコルチコトミーコース インストラクター
・(株)YDM 矯正器材アドバイザー
・ABO Journal Club 主宰
・Cutting Edge of Digital Orthodontics 主宰
*論文・学会発表
- ・加速矯正とアライナー治療による治療期間のコントロール ザ・クインテッセンス2022年11月号
- ・進化するデジタル歯科技術Extra モディファイドコルチコトミー法とSureSmileによる矯正治療 日本歯科評論 81(8)=946:2021.8
- ・進化するデジタル歯科技術 : 3Dプリンターは臨床をどう変革するか(4)矯正治療における3Dプリンターの臨床応用 日本歯科評論 81(4)=942:2021.4
- ・矯正用光重合型レジン系接着システムの接着性能 接着歯学2013年31巻4号P159-166
- ・歯科矯正学における3D診断および治療計画(翻訳)クインテッセンス出版
- ・基礎から学ぶデジタル時代の矯正入門(翻訳統括)クインテッセンス出版
- ・矯正歯科治療のためのコルチコトミー(翻訳)
- ・Effects of compression force on fibroblast growth factor-2 and receptor activator of nuclear factor kappa B ligand production by periodontal ligament cells in vitro. J Periodontal Res. 2008 Apr;43(2):168-73.
- ・Evaluation of the success rate of single- and dual-thread orthodontic miniscrews inserted in the palatal side of the maxillary tuberosity. J World Fed Orthod. 2022 Jun;11(3):69-74.
- ・T-helper 17 cells mediate the osteo/odontoclastogenesis induced by excessive orthodontic forces. Oral Dis. 2012 May;18(4):375-88.
- IL-8 and MCP-1 induced by excessive orthodontic force mediates odontoclastogenesis in periodontal tissues. Oral Dis. 2011 Jul;17(5):489-98.
- ・Effects of HSP70 on the compression force-induced TNF-α and RANKL expression in human periodontal ligament cells. Inflamm Res. 2011 Feb;60(2):187-94.
- ・Effects of relaxin on collagen type I released by stretched human periodontal ligament cells. Orthod Craniofac Res. 2009 Nov;12(4):282-8.
- ・Levels of RANKL and OPG in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement and effect of compression force on releases from periodontal ligament cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.
詳しいプロフィールはこちらより